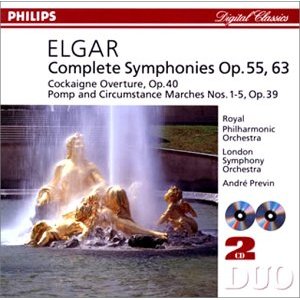ルーセル 交響曲第1番「森の詩」
先のエントリーで紹介したサティや、フランス音楽の双頭ドビュッシー、ラヴェルと同時代の作曲家、ルーセルの最初の交響曲。
1904年に完成し、1908年にブリュッセルで初演された。
第1楽章 冬の森 (Foret d’Hiver)、第2楽章 春 (Renouveau)、第3楽章 夏の夕べ (Soir d’Ete)、第4楽章 牧神と森の精 (Faunes et Dryades)という副題があり、冬→春→夏→秋という森の四季を描いた作品である。
「フランス山人の交響曲」で有名なダンディに師事。フランクからダンディ、ダンディからルーセルへと受け継がれた循環形式を用いた曲であると同時に、ドビュッシーのような描写的な印象派の響きを持った曲でもある。
この作品の素晴らしさは、各楽章の特徴的な季節描写はもちろんのこと、全体を通した循環性にある。
柔らかな靄を思わすバソン、フルート、クラリネットに弦楽器のうねりから始まる「冬の森」では、靄の中にオーボエの旋律が現れ、徐々に盛り上がりを見せると、金管が加わり、まるで靄をかき消すような寒々しい風が吹き荒れる。ドビュッシーに負けない見事な描写力である。
冬の空気の後には、快活な「春」の空気がやって来る。感情に響く弦楽の旋律、楽しげに動く木管とハープ、ピッツィカートが印象的だ。
「夏の夕べ」はたっぷりと歌われる旋律が特徴で、遠くから聞こえるホルン、ためらいがちな木管群の重なりが、この情緒的な旋律と絶妙に絡み合う。
最終楽章「牧神と森の精」は少し長めで、ノクターンである「夏の夕べ」と対照的な動きのある音楽だ。
打楽器も効果的に使われ、色鮮やかで表情の豊かな楽章になっている。
華やかさがクライマックスを迎えると、盛り上がりは徐々に鎮まる。牧神と森の精たちが名残惜しそうに去って行く様が目に浮かぶ。
そして音楽は、またしても柔らかな靄を思わす雰囲気を迎える。秋も終りが近づいたということだ。
作品としてはこれで終わりだが、この4楽章の後にもう一度最初から聴いても、全く違和感がない。完全に循環しているのだ。
人間たちの世界では、季節が巡ってくるごとに様々な変化があるのだが、人間の手の届かぬところ――牧神や森の精のいるところは、ひとつの完全なる「美の世界」なのだろう。
そんなことを思わせてくれる、美しい交響曲だ。
 |
ルーセル:交響曲全集 デュトワ(シャルル),ルーセル,フランス国立管弦楽団 ワーナーミュージック・ジャパン |
 Author: funapee(Twitter)
Author: funapee(Twitter)都内在住のクラシック音楽ファンです。コーヒーとお酒が好きな二児の父。趣味は音源収集とコンサートに行くこと、ときどきピアノ、シンセサイザー、ドラム演奏、作曲・編曲など。詳しくは→more