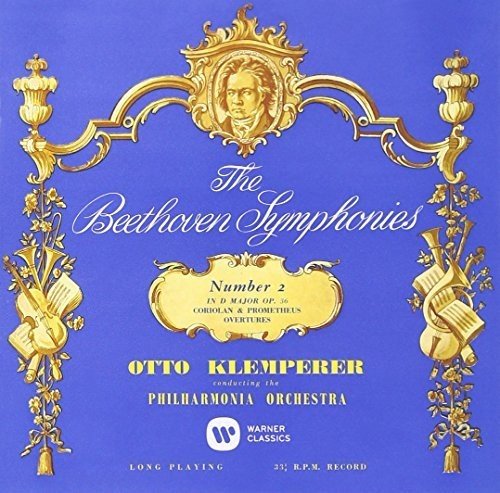ベートーヴェン ピアノ三重奏曲第7番 変ロ長調 作品97「大公」
「ベートーヴェンの器楽は巨大で計り知れないものの領域を開く」これはE.T.A.ホフマンの言葉である。この言葉がまさに当てはまる曲を取り上げよう。
最近マイナー曲ばかり書いているが、2020年はベートーヴェン生誕250周年である。僕はシューベルトやシューマン好きを公言していますが、実は記事の更新数ベートーヴェンが一番多い。やっぱり好きなんだなあ、と。
ということで、ピアノ三重奏曲の傑作、通称「大公トリオ」。そこそこ有名なので各所に様々な情報があり、今更何を書こう。そこで、みんなが「大公トリオ」を調べるときにどんな検索キーワードを入れているのかを見てみた。「難易度」「解説」「名盤」などの他に、「海辺のカフカ」「幽霊トリオ」「街の歌」「ケンプ」「オボーリン」「スーク」と出てくる。
村上春樹の『海辺のカフカ』にこの曲が登場したのはぼんやり覚えている。おかげでリスナーも増えただろうし、嬉しい話だ(よろしければ「ハルキストと話したときのこと」もお読みください)。ルービンシュタイン、ハイフェッツ、フォイアマンの通称「百万ドルトリオ」の録音だ。
「幽霊トリオ」は以前ブログで取り上げたし、「街の歌」も名曲。やはり副題や愛称があるといかに手に取りやすくなるのか、よくわかる。
「スーク」のトリオは有名で、「ケンプ」もベートーヴェンの権威だ。「オボーリン」はやや意外だが、オイストラフ、クヌシェヴィツキーとの「オイストラフ・トリオ」でピアノを務めたロシアの大教授である。
百万ドルトリオ(1941年)、スーク・トリオ(1983年)、オイストラフ・トリオ(1958年)、もちろんケンプとシェリングとフルニエの録音(1970年)も、どれも「大公」の名盤だろう。しかしまあクラシック音楽界隈は、関心が20世紀で止まっているんじゃないかと心配になるね。もう21世紀始まって20年も経つのに……。
まあ名演の話は別に書くとして、曲の話をしよう。4楽章構成、40分もある大作であり、とにかく曲の始まりから終わりまで、徹頭徹尾、余裕を感じるというか悠々たる自信に満ちているというか、絶妙なバランス感覚、品位、高潔さをまとう傑作である。ルドルフ大公に献呈したため「大公」と愛称が付いており、この曲の雰囲気が一般名詞としての「大公」のイメージにもぴったり合っていることも、長く愛される人気作となった理由だろう。
1810年の終わりに着手、翌年3月には完成し、ウィーンで非公式の初演を行った。公開初演は1814年、シュパンツィヒのヴァイオリンとリンケのチェロ、そしてベートーヴェン自身のピアノで演奏された。耳の病はピアノ演奏に支障をきたしており、初演を聴いたモシェレスやシュポーアは、ベートーヴェンの演奏技術の劣化を嘆きつつ、それでもなお称賛すべき点も残っていたと語っている。数週間後にこの曲を再演し、それがベートーヴェンにとって最後の公の場でのピアノ演奏となった。
1楽章の第1主題、ベートーヴェンにしてはやや長めの、叙事詩の幕開けのごとき旋律。単純にこのメロディの美しさだけとっても成功作に違いないが、dolceのピアノから始まるのも、なんというか「がっつかない」余裕のような、鷹揚な品の良さを感じる。徐々に弦が重なり合い、主題が繰り返されるときにはヴァイオリンが主旋律になるのも鉄板だが素敵だ。弦の入り方も、奏者によってはぬるっと入ってこられると妙な不気味さもあり「こっちが幽霊トリオか!」とツッコミを入れたくなる。
2楽章のスケルツォ、伝統的なピアノ三重奏曲は3楽章だが、交響曲のごとくスケルツォ楽章が挿入され規模が大きくなっている。冒頭のホフマンの言葉を思い起こす。単純に曲の長さだけでなく、僕はこのスケルツォ楽章を聴いて「ああ、これオーケストラ版で聴いてみたいな」なんて思ってしまうのだが、そんなときにベートーヴェンの「巨大で計り知れないものの領域」を切り拓いていこうというスピリットを感じる。変化が多くて楽しい楽章だが、個人的には主題の旋律の愛らしさによるところが大きいように思う。優雅さもある。
ピアノから始まる3楽章も、ベートーヴェン作品指折りの美しいアンダンテ・カンタービレだ。ロマンティックだが大げさでないのは、この曲全体に共通する品の良さによる。テクスチャが厚ぼったくならず、まるですきバサミですいたような軽さがあるからだろう。その分、細かい連符やリズムの活用が効いており、変奏の技も豊富に見れる。
4楽章、大げさにやってフィナーレを盛り上げることもできるだろうが、一つ一つの要素はベートーヴェンの他のピアノ三重奏曲よりもいっそう洗練されているため、上品な雰囲気を保って演奏するスタイルも非常にマッチする。燃え上がる情熱でぶっちぎるぞ、というだけではないのが、この曲の魅力だ。
ヴァイオリンの音域がやや低め、チェロもかつての古典派より活躍、そしてベートーヴェン自身とルドルフ大公が弾く楽器であるピアノの使い方の巧みさ、これらによってグッと大人っぽい(という表現が良いのかわからないが)雰囲気になっている。
ベートーヴェンの音楽に宿る「精神性」なるものを信奉するのであれば、おそらくこの曲からも、偉大なる自然の神秘や、その中に生きる人間の喜び、光と闇の内なる葛藤、そして最終的には人類愛や無限なる歓喜、平和と調和、そうしたものを見出すことは可能だろう。
しかし僕はもっとプライベートな音楽に聴こえる。ルドルフ大公へのリスペクトを込めた贈り物。ロマン派の音楽の先取りのようだ。少なくともこの曲から漂う上品さは、人類一般というよりは一個人のもつ内面によるものに感じるのだが、どうだろうか。ベートーヴェンの器楽が開く「巨大で計り知れないものの領域」とは、そういう音楽の新時代のことも示唆しているのかもしれない。
【参考】
僕はホフマンの言葉を切り取って用いて、適当に自分の言いたいことを言っているだけですので、文脈込みで見たいという方はぜひ調べてみてください。
Hoffmann, E.T.A.(transl. Bryan R. Simms.), “Beethoven’s Instrumental-Musik,”(1813) in E. T. A. Hoffmanns sämtliche Werke, vol. 1, ed. C. G. von Maassen, Munich and Leipzig: G. Müller, 1908.
 Author: funapee(Twitter)
Author: funapee(Twitter)都内在住のクラシック音楽ファンです。コーヒーとお酒が好きな二児の父。趣味は音源収集とコンサートに行くこと、ときどきピアノ、シンセサイザー、ドラム演奏、作曲・編曲など。詳しくは→more