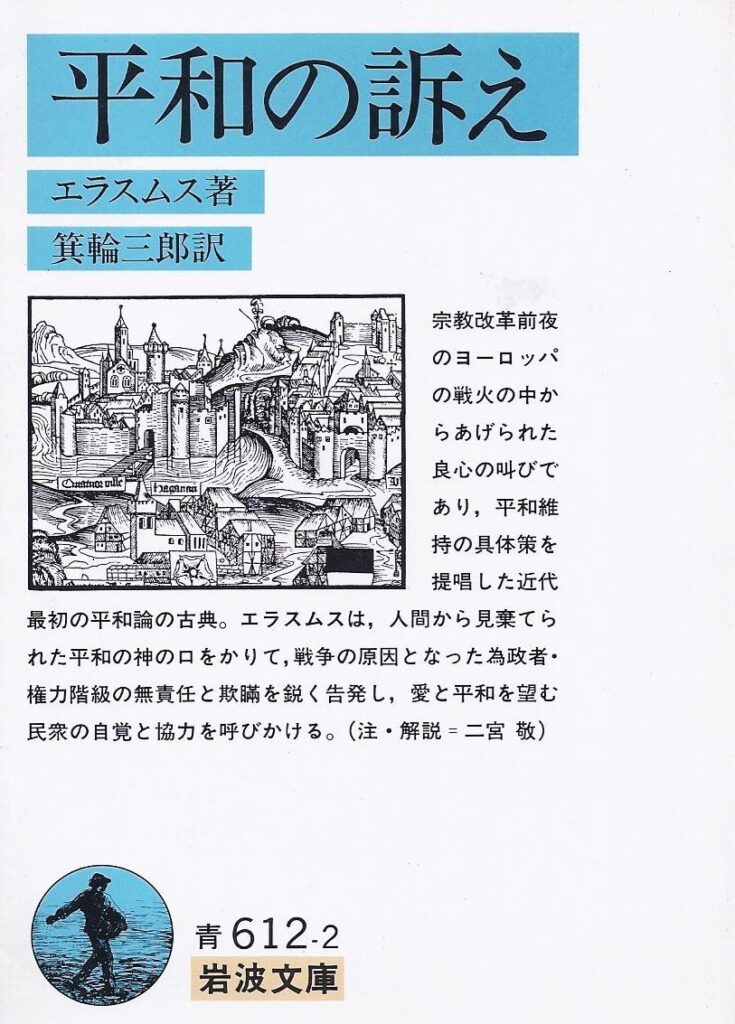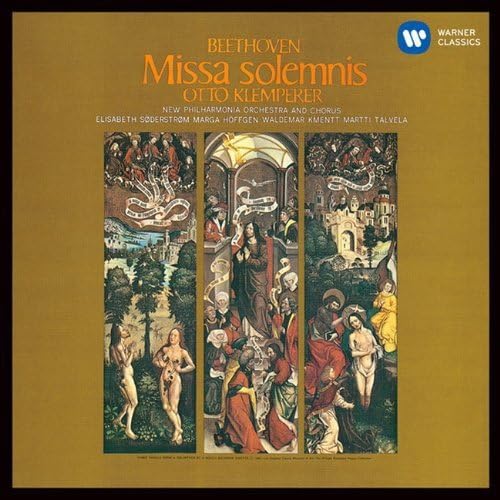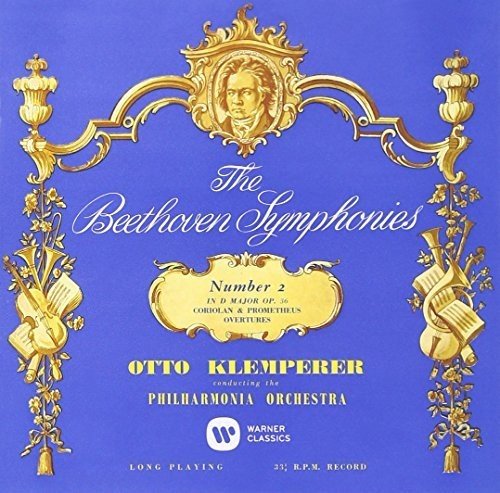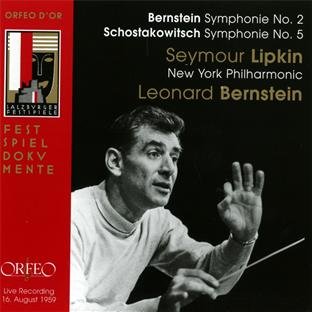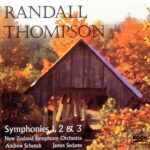ドラティ 交響曲第2番「平和の訴え」
アンタル・ドラティ(1906-1988)は自身の創る音楽についてこう語った。
「すべての芸術がそうであるように、私の音楽もまた未来を指し示している。だが実質的には現在による、現在のために創られた音楽であって、抽象的に分離したものではなく経験のまん真ん中で、ある特定の目的のためではなくただ聴かれるために創られた音楽だ。ベートーヴェンは『心より出で-願わくば再び-心に向かうよう』と言った。彼は音楽の真実の、中心の、そして唯一の意味、存在意義を、この短文で明確にした。彼は最も偉大な創造の天才の一人として、そのように宣言することができたのだ。小さな小さな才能では、この文を語ることすらできないかもしれない。しかし、それでも考え、体験しなければならない。そうでなければ作曲家として、人間として、端的に説得力がない」
ドラティの交響曲第1番と第2番の録音(BISレーベルの自作自演CD)のブックレットで、ドラティ自身が楽曲解説をしている。曲の解説に作曲家自身が適した人物なのかというと心から疑問だ、とも言っている。「自分が創ったもの」ではなく「自分が創りたかったもの」について話してしまうのではないか、と。まあそれならそれでも良いかと開き直って書いているのだが。
元々作曲も好きだったドラティは、音楽家の父から「作曲家では食えないかもしれないから定職を得ろ」と言われ、歌劇場の指揮者なども務めつつ作曲も行うというキャリアだった。ただ指揮者として膨大な録音を残した結果、現代ではそちらのレガシーのみが顧みられているという状況だ。
様々な編成の曲を残したドラティだが、中でも代表作と呼ばれるのが、この交響曲第2番「平和の訴え」だ。
ドラティは、75歳まで音楽監督を務めていたデトロイト交響楽団から、80歳の誕生日に初演する作品を依頼された。何を書くかは自由だったため、ドラティはかねてから思っていた、「自分が書くならば平和のシンフォニーでなければならない」という思いを実現させたのだ。
このドラティの思いは、自身が長年に渡って音楽家として、人間として成長してきたことと関係があると語る。人類が破滅に向かっていると年を重ねるごとにわかってきたし、芸術はそれから逃げてはならない。我々の時代における最大の重荷は、増大する不安、平和の欠如、そして大いなる消滅の脅威である。これを防ぐことが我々の義務であり、思慮深い人々はそれぞれの方法でそれを支援しなければならない。芸術家はその芸術によって……と、ドラティは考えていたのだった。
それをどのような方法で音楽にするか思案していた頃、1985年4月、ドラティはアムステルダムのベートーヴェン通りにある書店のディスプレイの前でふと立ち止まった。そこにはエラスムスの『平和の訴え』(Querela Pacis)があった。それを見た瞬間、ドラティは学生時代に読んだその感動的なエッセイのことを思い出した。そうだ、私の交響曲第2番は「平和の訴え」のようなものだ……というインスピレーションから作曲が進んでいった。
1985年8月に完成し、翌年4月にギュンター・ヘルビッヒ指揮デトロイト響によって初演された。3楽章構成だが休みなく演奏される。演奏時間は30分弱。また副題はあくまで印象を喚起するものであってエラスムスの著作の内容とは関係なく、何かを描写している音楽ではないとドラティは説明している。
第1楽章“Peccata Mundi”、世の罪という意味。不安、降伏を象徴する弦楽に続き、重々しい金管の行進、木管の悲鳴。常に不協和音という訳ではなく、嘆きの歌には悲しい美しさもある。ティンパニが特徴ある動きをするのも興味深い。この曲は全体を通してティンパニが非常に重要である。
切れ目なく続く第2楽章“Dies Illa”、よく見ると「怒りの日」ではない。“Dies irae, dies illa”の、「あの日」の方である。この交響曲はどの楽章も怒りの日の旋律が引用されており、様々に扱われているし、この楽章が争いの気配に満ちているのは確かだ。ドラティいわく、音楽は警告を与えるだけで、惨状そのものを見せることはない、と。この楽章の激しく歪な響きは破滅の描写ではなく、破滅の訪れを語る預言のようなものなのだろう。
そしてこちらも切れ目なく続く第3楽章“Dona Nobis”、我らに与え給え。普通はDona nobis pacemと書くところだが、Pacem(平和)は何処へ? 3楽章が全体的に静かで穏やかな音楽であることはすぐにわかる。争いは終わったのだろうか。ここで単に、争いが終わり平和が訪れるという単純なハッピーエンドを提示するだけで終わらせないのが、ドラティの凄いところである。確かにこの楽章は平和の歌だ、だがしかし、それはまだ本当の意味で我々のものではない。どこからともなく、いや、心の内から知らぬうちに聴こえてくる旋律が、徐々に賛美歌へと成長していく……この楽章はそんな音楽である。心の内にある旋律は何か。それはもちろん、1楽章でも2楽章でも、悲痛な旋律だった「あの日」である。ドラティは語る。我々は「あの日」を「怒りの日」と想像することに慣れすぎてしまった、ここでは「平和の日」として認識することになる、と。なるほど、そんなことを思わせる音楽である。確かにこの旋律は、もしかすると、我々次第で平和の日にもなり得るのではないか、いや、これを平和の日にするのが、神ではなく人間の精神活動の務めなのではないか……そんなことも思ってしまった。
平和の歌が鳴り響くまでの間に、それを手助けするようなある美しいフレーズが、弦楽四重奏によって奏でられる。それはベートーヴェンのミサ・ソレムニスからの引用である。アニュス・デイで、“Pacem”と歌われる優しい旋律だ。Pacemはここにいたのだ、天国から聴こえる、ベートーヴェンの声の中に。これが何を意味するか、多くを語る必要はないだろう。「心より出で-願わくば再び-心に向かうよう」、ドラティの交響曲は、我々に静かに訴えかける。平和とは?
 Author: funapee(Twitter)
Author: funapee(Twitter)都内在住のクラシック音楽ファンです。コーヒーとお酒が好きな二児の父。趣味は音源収集とコンサートに行くこと、ときどきピアノ、シンセサイザー、ドラム演奏、作曲・編曲など。詳しくは→more