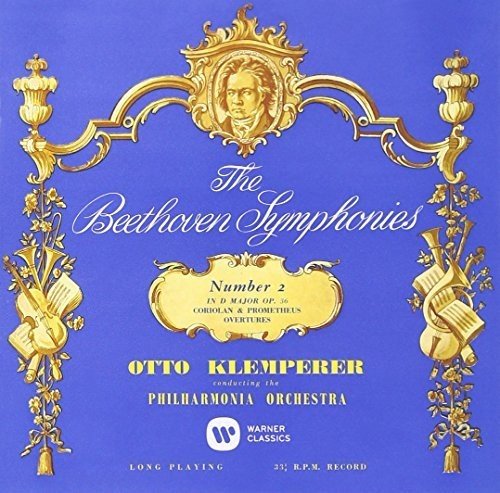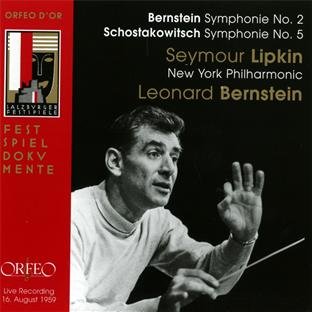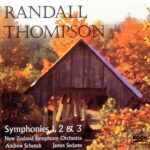ヒェレモ 交響曲第2番 ロ短調
久しぶりに東京でも積雪したので、寒い地域の音楽、北欧の音楽を取り上げることにしよう。オーレ・ヒェレモ(1873-1938)というノルウェーの作曲家を知っている人は非常に少ないのではないだろうか。記事冒頭にリンクを貼ったCDは2023年リリース、ごく一部の北欧マニアを除き、それまでほとんどのクラシック音楽ファンは存在すら知らなかったものと思われる。
ヒェレモはノルウェーの小さな山村、ドブレで生まれた。「ドブレ」で検索すると薪ストーブのメーカーが出てくる。ドブレ社はノルウェーのドブレ山脈に由来する名前だそうだ。このCDに描かれているのもハラルド・ソールベリ(1836-1925)という画家によるドブレの山々である。ヒェレモはまさにそんな大自然の中で育った。父は農民(小作人)でありまた仕立て屋も営み、子どもたちも農作業を手伝うのが普通、そういう農村文化の中で育っている。
ノルウェーの有名な作曲家というとグリーグやスヴェンセンが思い浮かぶが、この人達は基本的に大都市で生まれ、音楽院でしっかり学びドイツ留学もしている、いわば都会人である。我々が彼らの音楽から感じる北欧の民族音楽的な要素というのも、彼らはどちらかというと最初から持ち合わせていたというより、後になってその伝統的文化の価値を「発見」したという方が正しい(グリーグの交響曲の話も参考にしてほしい。以前ピアノ・ソナタの記事を書いたときに触れている)。しかし、ヒェレモは本当に日常生活において民族音楽に囲まれて育った音楽家である。父親もフィドルを弾いたし、ヒェレモが初めて手にした楽器は6歳のとき、父が作った自作フィドル、そのとき既に音楽の才能は天才的だった。ヒェレモがいつ音楽の道を志すようになったかは不明だが、当時、また当地で「都会に出て音楽家として生きていく」という道を思いつくことの方が不思議なくらいの田舎であり、おそらく誰かしらの助言があったのだろうが、その辺は未だ不明らしい。ただ、音楽の才能に驚いたヒェレモの父は、お金もないので、自らが仕立てたスーツと物々交換で古い本物のヴァイオリンを手に入れて子に与えたそうだ。これがFant-Kalという19世紀の伝説的フィドル奏者が使用していたもので、今は博物館に飾られているとのこと。この楽器を用いて村の結婚式や祝宴で弾きまくったヒェレモは、ドブレだけでなく遠方からも呼ばれる腕前だった。
この時代の北欧の小さな山村からシンフォニストが現れるというのは、別に詳しく調べている訳じゃないけど、相当珍しいことなのではいだろうか。音楽以外でも、また現代においても「都会に生まれていれば……」と自身の生まれた田舎を恨みたくなる気持ちは、田舎から出てきて東京で暮らす僕はそれなり理解しているつもりで、都会育ちが何の気なしに言う「そんなに田舎が嫌なら都会へ出たらいいじゃないか」という有り難いアドバイスだって、実は彼らの想像を遥かに超える難しさなのだと、多分田舎生まれでないとその辺の感覚はわからないだろう。中々出るのは容易でないのだ。まあ出たお前が言うなと言われたらまあそうなんだけど……ともかく、今でさえそうなんだから、19世紀末の北欧の山村なら尚の事だ。
1893年、20歳のヒェレモはドブレを離れオスロ(当時クリスチャニア)へ。1883年にオスロ音楽院がリンデマン親子によって開かれていたとはいえ、田舎から出てきた貧乏青年がするっと入れる訳もなく、ひとまず軍の学校へ入学、少ない給料を貰いながら軍楽隊に所属し音楽を学ぶことができた。成績優秀、首席で卒業。軍楽隊の指揮者、作曲家でもあるオーレ・オルセン(1850-1927)はヒェレモを手厚く支え、他の有名教師も呼んで熱心にレッスンした。ヴァイオリニストとして舞踏会やオーケストラなど様々な場所で演奏するようになると、その腕前は評判で、主要オケや国立歌劇場の奏者も務めるようになる。30歳からは市内の音楽院で指導もするようになった。大出世したヒェレモ。ドブレの人たちは「音楽で稼ぐために村を出ていった若者」を当時どう受け止めたか定かではないが、ヒェレモは毎年夏になると必ず地元に帰って過ごしていたとのこと。生涯母国を出ることはなく、地元や家族との関係も良好だったそうだ。
舞踏音楽をはじめ作曲も沢山している。交響曲、協奏曲、合唱曲、吹奏楽など幅広い。編曲ものや、民謡を用いたものからオリジナルまで相当色々書いたそうだ。残るものの中で最も古いのは1896年に書かれた軍楽隊向けの行進曲。1912年に作曲した交響曲第1番は50分もの大作で、ヨハン・ハルヴォルセン(1864-1935)指揮、国立歌劇場管で初演。指揮者や奏者、聴衆からも好評だったが、批評家からは酷評される。初演から25年経った1937年に改訂を始めるも、1938年に他界。以降はヒェレモの音楽も忘れ去られていく。こうして2023年になって録音が出たのは嬉しい話だ。演奏はヨルン・フォスハイム指揮マクリス交響楽団、2022年録音。ヴァイオリン協奏曲と、同じくヴァイオリンとオーケストラのための協奏作品である「ノルウェー奇想曲」はクリストファー・トゥン・アンデルセンが独奏ヴァイオリン、そして1926年に書かれた交響曲第2番ロ短調を収録。これも50分近くある大作交響曲で、当時のノルウェーでこの規模の交響曲は珍しいだろう。
先程も触れた通り、ヒェレモは民族音楽が根底にあり、その後から徹底的に西洋芸術音楽を学んだ作曲家である。その辺を踏まえて聴くと、ちょっと他の北欧系シンフォニストの交響曲との違いも見えてくるかもしれない。あるいは結局スタイルが融合したら同じなのか、と思うかもしれない。交響曲第2番は標題音楽ではないが、ヒェレモ自身がインスピレーションになったものについて言及している。この曲は登山から影響を受けており、第1楽章は五度の下降による「山のモチーフ」や、牧畜民が牛を呼ぶときの歌などがも用いられている。リヒャルト・シュトラウスのアルプス交響曲、以前ブログに書いてたラフの交響曲第7番「アルプスにて」のような山の交響曲ほど直接的な描写はない。しかし、それらが好きな人ならきっとこの交響曲も気に入ると思う。名だたる作曲家たちよりも誰よりもずっと山を知っている、そんな人が西洋音楽の手法を身につけて書いた交響曲なのだから。
あまり発言記録の残っていないヒェレモだけども、ブラームスとワーグナーは好きだったという発言はあり、この曲の随所で、もう第1楽章からそんなオーケストラ/交響曲の大家たちに倣った管弦楽法やフレーズを聞き取ることができる。第2楽章は緩徐楽章、霧とそこに差し込む日差しのようなものを想像できるだろう。素朴なダブルリード、突き刺すような金管、クラリネットやフルートの穏やかな表情など、卓越した楽器法も見られる。弦楽の扱いも非常に奥深い、ここではワーグナーの物語とブラームスの精神が喧嘩せずに同居している。
第3楽章はスケルツォ楽章、中間部に現れるのどかな牧歌的なメロディが美しいし、構成も良い。フィナーレの第4楽章、初めに主題の回帰も見せ、基本は穏やかで静かに流れる、まるで小川に沿って下山するかのようだ。爆発的な終曲ではないが、独特のリズムや音色が次から次へと湧き出て流れている、少し変わった音楽。ヴァイオリンとチェロがソロで掛け合いをするのも美しいし、様々な楽器が入れ代わり立ち代わり活躍する色彩感も良い。勝利の凱歌や熱狂の舞曲ではないが、不思議と自然の美しさに感動できる、この辺りはやはりシベリウスが近いかもしれない。白樺の木立を抜けたら、静かに消え入るように終幕。実にいい。登山を描いている訳ではない、あくまで、登山からインスピレーションを受けた標題のない交響曲。この第4楽章は一見すると交響曲の終わりとしてはちょっと弱いというか、物足りない気がするが、何度も聴いてみてほしい。創られた大スペクタクルとは違ったその面白さ、創造性に気づくだろうし、これが非常に卓越した交響曲だと納得できるはずだ。1926年の初演は好評で、批評家たちも第1番よりは評価したという。それから100年近く顧みられなかった交響曲。ぜひ聴いてみてほしい。
 Author: funapee(Twitter)
Author: funapee(Twitter)都内在住のクラシック音楽ファンです。コーヒーとお酒が好きな二児の父。趣味は音源収集とコンサートに行くこと、ときどきピアノ、シンセサイザー、ドラム演奏、作曲・編曲など。詳しくは→more