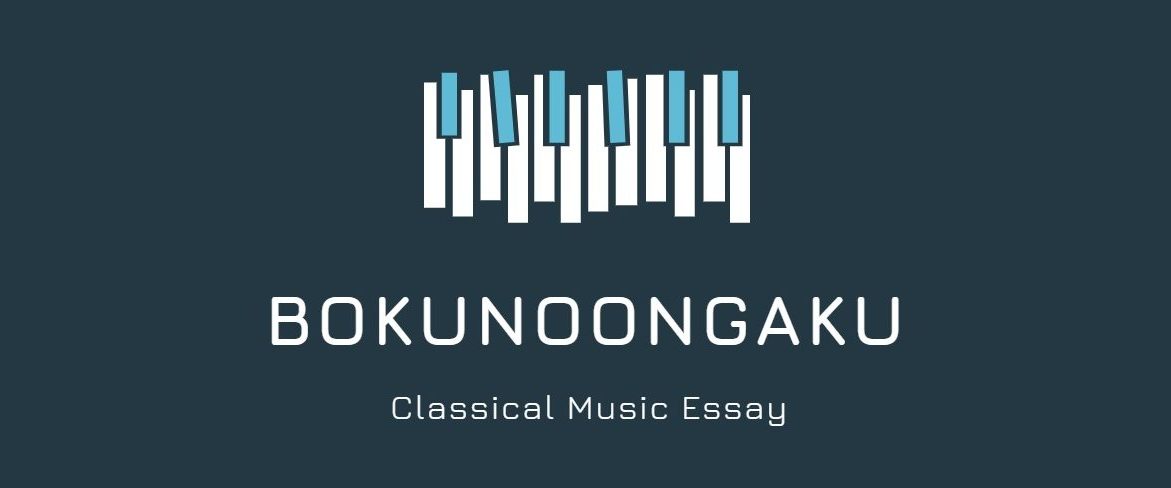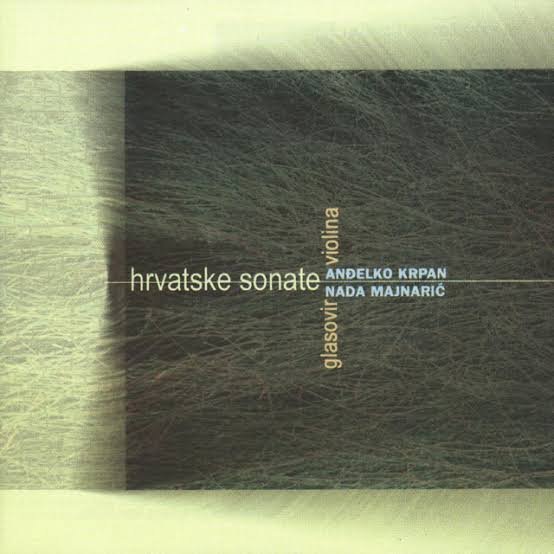スラヴェンスキ スラヴェンスカ・ソナタ
とてもマニアックな話になるので読む人も少ないだろうと思い、普段より好き勝手書かせてもらおう。いや、いつも好き勝手書いてるけど……。ヨシプ・ストルチェル・スラヴェンスキ(1896-1955)はクロアチアの作曲家。クロアチアというか、ユーゴスラビアだが。チャコベツ生まれ。
日本での知名度は低く、全くもって日本語表記の慣例もないため、単にスラヴェンスキではなく、ストルチェル=スラヴェンスキと書かれる場合もある。日本語のWikipediaではストルチェル=スラヴェンスキと一続きになっている。これは恐らく英語版WikipediaでJosip Štolcer-Slavenski(セルビア語キリル文字ではЈосип Штолцер-Славенски)と表記されているので、それに倣ったのではないだろうか。セルビア・クロアチア語版WikipediaではJosip Slavenski、本名がJosip Štolcer-Slavenskiと書かれている。WikipediaのURLは前者の表記であること、本名が後者なら普段使いする通称は前者なのだろうということ、そして同語版Wikipediaに掲載の碑の写真を見てもハイフンで繋がっていないこともあり、ここでは「スラヴェンスキ」単独での表記を採用することにした。小さい子が映り込んでいて微笑ましい。

なぜこんなことを前置きとして書いているかというと、マニアックな人ほどこういう細かいところを気にしがちだからだ。別にそういう人のことが嫌いなのではなく、何を隠そう自分がそうだからである。ただ、僕が「まだ日本語でほとんど書かれてないんだし、どっちでも良いのでは」と思っていても「いや、ストルチェル=スラヴェンスキが正しい名前である、あなたは間違っている」と野暮な指摘をする人がいるかもしれない。なので、表記を採用した理由を一言付しておこう、という意図だ。僕はヴォーン=ウィリアムズが大好きなので、もし「ウィリアムズ」って名前で書かれていたら嫌だし、そういう気持ちはよくわかっているつもりだ。全国のヨシプ・ストルチェル・スラヴェンスキ大好きクラブの皆様、何卒ご了承ください。
もう少し詳しく言及すると、父親の姓がストルチェル、母親の姓がノヴァークだそうで、20代の頃から姓をストルチェル=スラヴェンスキと書くようになったそうである。これはスラヴェンスキがユーゴスラビアの理念に傾倒していたのと、ドイツ語らしい姓への拒絶の、両方があったとのこと。とすると、スラヴェンスキというのはペンネーム的なものに近いかもしれない。スラヴ人であるというアイデンティティの現れでもある。
今回取り上げるのはヴァイオリンとピアノのための作品、スラヴェンスカ・ソナタ。ここでもちょっと言葉の話題に触れておく。Schottの出版譜はSLAVENSKA SONATAとSLAVONIC SONATAの併記であり、意味としては「スラヴのソナタ」というところ。slavonicという英語はスラヴのという意味で良いだろうし、チャイコフスキーのスラヴ行進曲(Slavonic March)や、ドヴォルザークのスラヴ舞曲集(Slavonic Dances, チェコ語ではSlovanské Tance)でもあるように、スラヴ◯◯という日本語の曲名が良さそうだ。しかしスラヴソナタと書くのは、ちょっと不自然な気がする。例えばスラヴ交響曲やスラヴ協奏曲であれば違和感ないのだけど、カタカナ同士が繋がるとなんか嫌だ。漢字を挟んで「スラヴ風ソナタ」なら見た感じ良さそうだけど、スラヴ「風」じゃなくて、スラヴそのものである。「風」とすると嘘っぽい。では「・」を入れて「スラヴ・ソナタ」はどうか。こっちの方がありそうではある。よし、「スラヴ・ソナタ」にしてブログ書こう!と思うも、SLAVENSKA SONATAとSLAVONIC SONATAという題をもう一度見て、これを「スラヴ・ソナタ」にするのはなんか削ってしまうようで、違う。で、結局、カタカナのあり方そのままに、スラヴェンスカ・ソナタにした。自分でも思う、マニアックな人はこういうとこが面倒なんだよ。言った通りでしょ。繰り返すが、意味としては「スラヴのソナタ」だ。「スラヴェンスキさんのソナタ」という意味ではない。スラヴェンスキさんのソナタだけどね。
スラヴェンスキの音楽を知っている人からしたら、なぜこの曲を挙げるのか、オリエンタル交響曲でもバルカン組曲(バルカノフォニア)でも弦楽四重奏曲集でもなくてこの曲なのか、と思われるかもしれない……うーん、思われるかな、まあ、もしそんなことを少しでも思った人がいたら多分同志であろうよ、僕よりお詳しいかもしれない、そっとしておいてくれ。
オリエンタル交響曲はそもそもそんなに好きではない。バルカノフォニアも弦楽四重奏曲集も大好き。ただ、普及したいという目的の上では、なるべく編成の小さいものの方が気になった奏者の人にとっては始めやすいだろうなと思ったからだ。オケだとなかなか難しいでしょう。それとは別に上記のような「スラヴ」というキーワードに触れているからなのもあるし、普通に曲が大好きだからという理由も当然ある。10分にも満たない単一楽章のソナタで、大変濃厚な音楽だ。
ブダペストでコダーイに、プラハでノヴァークに師事したスラヴェンスキ。その後パリに留学し、1923年にザグレブで音楽教師となり、1924年にベオグラードに移住。このスラヴェンスカ・ソナタは1924年の初め頃に作曲されたと考えられている。クロアチアのヴァイオリニスト、ズラトコ・バロコヴィッチに献呈。
スラヴェンスキの他の多くの作品のように、開幕一番でのインパクトの大きさは凄い。ピアノのオクターブで強く始まり、不思議な響きのアルペジオに、ヴァイオリンが民謡風の旋律を朗々と歌い始める。このピアノの使用がかなり特徴的である。リストのような雰囲気もあるが、リストほど洗練された印象を受けず、とは言え調性感を敢えて消そうとするような意図もなく、むしろ現代の小洒落たポップスでお飾りに使うときのケバケバしさのような、そんな印象を受ける。臆面もなくそういう音が鳴るのは、ある意味で小気味よい。
ソナタというだけあって、形式もこだわっている。もちろん古典派以降の伝統的なソナタではなく、異なる二つの対立関係と発展が、異様に極端に、そして唐突に行われる。それらが、スラヴェンスキの故郷の民謡に由来するであろう音階や調性でもってまとめ上げられている。協奏曲のようなカデンツァまで付いている。カデンツァを中央に置き、その前後では締め上げるような強い緊張感のある部分と郷愁を感じる情感たっぷりな部分と、良い相互関係。どういう訳か、この渋い民謡風の歌が妙に琴線に触れる。Grave lamentoso のヴァイオリンのメロディはグッとくる。まるで久石譲でも連れてきたのかと思うほどだ。さながら「もののけ姫」である。やっぱり海よりも山が思い浮かぶのが、クロアチア北部の生まれと関係している、かどうかは知らない。前半と後半で転調して二度登場する。そのメロディもまたピアノで風変わりな変化をする。そういうのも面白い。
クロアチア国民楽派の作曲家と言われるスラヴェンスキ。いわゆる後期ロマン派から少し逸脱した、大胆な表現をする面白い作曲家だ。密度の高い音楽。内容という意味でもそうだが、音の数でもそうだ。この曲でもピアノの厚みある和音が多様され、また不協和音の連打もあり、他の曲でも見られるけれどもクラスターの使用においてはヨーロッパの作曲家の中でも早い方だと思われる。
こういう作風の曲が何十分とあると聴く方も疲れるというか、あまり一般受けがよくない気もするけど、スラヴェンスカ・ソナタは10分弱の長さで、編成もデュオ、曲中のコントラストも大きく聴き映えもするしコンサート・ピースに良いのではないだろうか。もっとも、僕のようにふわっと語るだけなら気楽だけども、音楽的にしっかり深堀りすれば相当なレベルまで究められるだけの中身だとも思われる。しかしまあ、知られなければ埋もれたままなので、ぜひ気軽に聴いてみていただきたい。サブスク配信にも音源あります。
 Author: funapee(Twitter)
Author: funapee(Twitter)都内在住のクラシック音楽ファンです。コーヒーとお酒が好きな二児の父。趣味は音源収集とコンサートに行くこと、ときどきピアノ、シンセサイザー、ドラム演奏、作曲・編曲など。詳しくは→more