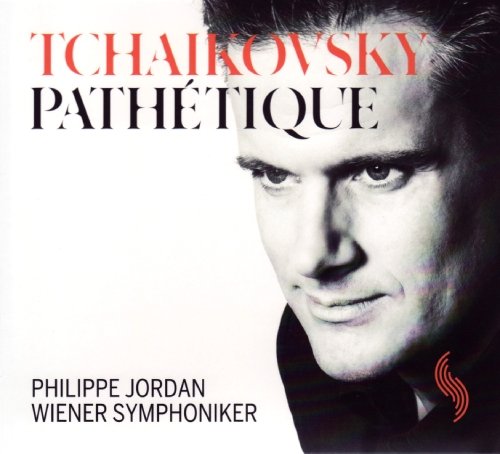オススメの名盤はこちら。
 |
ブラームス:交響曲全集(3枚組) ブラームス,エードリアン・ボールト,ロンドン交響楽団 Disky |
ブラームス 交響曲第1番 ハ短調 作品68
サー・エイドリアン・ボールト/ロンドン・フィル(1972年3月)
名盤として取り上げるには様々な条件があると思うが、これは歴史的な名演とか演奏技術が卓越しているとか、そういう類のものではない。これよりもずっと上手な演奏を数多く知っているし、記念碑的な演奏もそのうち紹介したいとは思っている。上に「オススメの名盤」などと書いてはいるが、もし僕が直接誰からオススメを聞かれたら、他の録音を先に薦めちゃうような気がするし、お世辞にも「これが最もオススメ!」などとは言えない。ではなぜ、ブラームスの第1番の名盤紹介トップバッターにエイドリアン・ボールトとロンドン・フィルを取り上げたのか。それは、僕がどうしようもなくこの録音が好きだからだ。そして、「是が非でも誰かに勧めたい」と思わせることはなくても、好きにさせるもの・惚れさせるものを確かに持っている、ということを多くの人に伝えたいのだ。
サー・エイドリアン・ボールト、好きな人は好きな指揮者だろう。世間的にはエルガーやヴォーン=ウィリアムズ、ホルストといった英国作曲家のスペシャリストという見方が一般的だ。日本のボールトファンはよく「ボールトは日本ではあまり評価されていないがヨーロッパでは評価が高い」と語る。では英国のファンはというと、「英国では評価されているが他のヨーロッパ諸国では正当な評価をされていない」という認識が多いそうだ。英国音楽界の独墺へのコンプレックスのようなものが窺い知れる。母国でのボールトの高評価の理由には、英国音楽の深い理解者であることに加え、ボールトが非常にドイツ音楽を得意にしていたということも挙げられる。おそらく、当時の英国指揮者の中で最もドイツ的な音楽作りを得意としていた指揮者であり、このブラームスの録音を聴けば、彼の演奏をヨーロッパのクラシック音楽の伝統の中心として捉えることに何の違和感もないとわかるはずだ。
とにかくこの演奏ほど「中庸の美」という言葉が似合うものもない。何一つ矩を越えることなく、それぞれの要素がそれぞれの持ち場で最大限のパフォーマンスを見せる。ボールトは1889年生まれ、この録音は1972年のものなので、当時は御年83才。1950年代~60年代にかけてもブラームスのチクルス録音を行っており、そちらの方がやはり勢いがあるが、オケも編集も、良くも悪くも大雑把。アプローチの仕方は新全集も旧全集もさほど変わりないが、録音や編集自体は、今取り上げている新全集の方がずっと良い。 何を隠そうこの録音には、ボールトの音楽性に惚れ込んだ名ヴァイオリニスト、ユーディ・メニューインが自ら志願してコンマスと2楽章のソロを務めている。だがしかし、そんな一大事すらまったくの些事に思えるほど、総合的な完成度の高さに驚く。この名盤のキャッチは「あのメニューインがコンマスに!」ではない。ここでは彼は主役ではなく、ひとつの音楽を作るチームの一員なのだ。

開始は重く、ティンパニの上にただただ正確なアーティキュレーションで奏でられる主題。良い。このシンプルさが良いのだ。当時としては珍しく提示部をリピートしているのも良い。実直である。思うにそれぞれの奏者にとっては、己の美学に基づいた思い思いの弾きやすい、吹きやすいテンポがあるわけで、ついそうやってはみ出した演奏をしてしまうという録音は多々あり、それが絶妙な味になっていたり、あるいは調和を乱す結果になったりする。しかしこの録音にはない。簡単に「ない」というより、そうならないように奏者が努めているのが伝わってくる。それがありありと伝わるのが良いことか悪いことかはさておき、「オレがオレが!」という自己主張ではなく「みんなのために!」という気持ちが伝わってくるのは、聴いていてなんとも「ほっこり」する。
2楽章のメニューインのソロも、ソロ・ヴァイオリニストとしてではなく、あくまでコンサートマスターのソロだ。メニューインならもっと怪物のようなソロを弾くことだって可能なはずだが、あくまでボールトの作る音楽の世界を支えるソロである。メニューインがボールトを慕って、それを意識して弾いているとしたら、泣ける話ではないか。まあ、もしそうでないとしても、全体としてこのソロは大成功している。3楽章のクラリネットのアルペジオが生み出す温もり。これが、英国音楽の録音で発揮されているボールトの最大の魅力のひとつだ。4楽章のフルートソロもべらぼうに美しい。今まで我慢していた(かどうかは知らないが)ものを「好きに吹いていいよ」と言われて解放したかのような、朗々と響く音。直後の金管のコラール、もう言葉が出ない。クライマックスにいたっては、切れ味こそないが、純粋純朴、終始紳士的な演奏に恐れ入る。少しはオオカミになっても良いんじゃないかと思うほど徹底している。これを「凡庸」と言う人には勝手に言わせておけば良い。だが間違いなく、ブラームスの音楽のあるべき形のひとつだ。
ではミスがない、隙のない完全無欠の演奏かと言えばそうではない。現代にはもっと上手い演奏がある。もっと言えば、当時にだってもっと上手いオケはあった。ロンドン・フィル、ロンドン・フィルか……独り言のようにつぶやいてしまう。なぜロンドン・フィルなのだ、ロンドン交響楽団は何をしていたのだ、いや、ベルリン・フィル、ウィーン・フィル、あなた方はなぜこの英国随一のドイツ音楽マスターを放っておいたのか……。カール・ベームに比肩する名演になった見込みはあれど、そんなことを言っていても仕方がない。これ以上言うとロンドン・フィルに失礼だし、ロンドン・フィルだからこその良さだってある。しかし、こんな恨み言を言いたくもなるほどボールトの音楽性、ことにブラームスの主要な管弦楽作品への理解は尊敬に値する。幼い頃から、ハンス・リヒターやアルトゥール・ニキシュという巨匠の交響曲演奏に触れ、彼らの音楽へのアプローチから受けた影響は大きいようだ。リヒターはブラームスの2番3番の初演を務めた指揮者である。ボールトがライプツィヒ時代に師事したニキシュからは、数多くのリハーサルやコンサートに触れ、多くを学んだ。また、フリッツ・シュタインバッハ、彼もブラームスの権威であるが、彼が1905年にロンドン響を指揮してブラームスの第4を演奏したコンサート体験が、6才のボールトに「将来は指揮者になる」と決意させたそうだ。ボールトのブラームス解釈からは、録音の残っていない巨匠たちの影を感じることもできるはずだ。
ブラームスの交響曲演奏の解釈には、無理を承知で大別すれば、フルトヴェングラーをはじめ古典様式とゲルマン精神の顕現のような魂燃える演奏、クレンペラーから始まり近年の演奏によくあるスコアをクリアに浮かび上がらせるようなブラームス作品の構造・構築の美を追求するもの、そしてバルビローリなど、様々な歌い方で旋律を美しくロマンティックに奏でるものがある。いかんせんブラームスは、過度にロマン的な演奏は似合わない、とまでは言わないものの、ブラームスも自身がメロディメーカーでないことは自覚していたし、ドヴォルザークやワーグナーと比べると「歌う演奏」はやはり曲の良さというよりも指揮者の演出の勝利という気がする。ボールトは、上に挙げたどれにも当てはまらない。他と比較すると本当に淡々としていて、演出皆無、特徴がないのが特徴と言える。そのくらいシンプルにやってこそ表出するブラームスの良さというものもある。そしてどこまでもどこまでも、親密な演奏だ。すべての演奏者、指揮者、聴衆が、全員知り合いのような、まるで家族の演奏を聴いているかのような温かさ、親密さがある。奏者から聴衆へという一方向の音楽ではない。ブラームスの交響曲第1番の本質はそういう親密な音楽なのだと思う、と以前ブログでも書いた(記事はこちら)。
この親密さもまた、交響曲の持つ「コミュニティを形成する力」のひとつではないか。音楽がえも言われぬ一体感を作り出すのに必要なものは、なにも圧倒的な高揚感だけではない。素朴で実直でありながら、常に優美で上品さを湛え、なおかつその場にいる者・その音楽に触れている全ての人をひとつにまとめあげる温かな音楽の力を感じる。その中心にいるのがサー・エイドリアン・ボールトだ。もしさらに興味を持ってくださったのなら、このスタジオ録音の4年後のプロムスでボールトがBBC響と共演したブラームスの録音も聴いてみていただきたい。スタジオ録音と同様、一見淡々とした演奏に思えるが、終演後の会場の興奮はひとしおだ。
この演奏に19世紀末の幻影を見出そうとするのは滑稽だろうか。懐古趣味と言われればそれまでだが、ボールトが本当に良い独墺クラシックの伝統を受け継いだからこそなし得た演奏だと思う。ピリオドとはまた違う、時代の香り。メニューインが感銘を受けるほどのボールト音楽性をたっぷりと堪能しよう。
 |
エイドリアン・ボールト – ブラームス:交響曲第1番ハ短調 Op.68/エルガー:創作主題による変奏曲「エニグマ」Op.363 エイドリアン・ボールト,ブラームス,エルガー,BBC交響楽団,ジョージ・タルベン・ボール ICA CLASSICS |
 Author: funapee(Twitter)
Author: funapee(Twitter)都内在住のクラシック音楽ファンです。コーヒーとお酒が好きな二児の父。趣味は音源収集とコンサートに行くこと、ときどきピアノ、シンセサイザー、ドラム演奏、作曲・編曲など。詳しくは→more