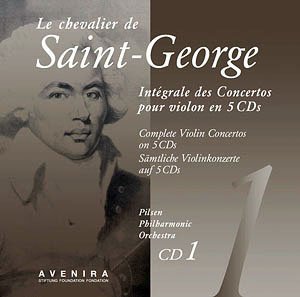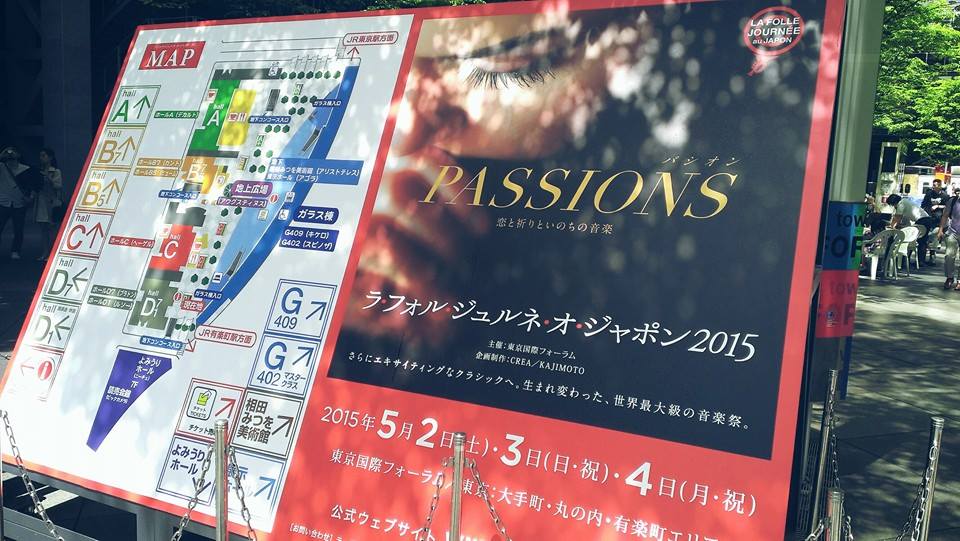ベルク ヴァイオリン協奏曲 ある天使の思い出に
初めてこの曲を聴いたときは衝撃が走ったものだ。
シェーンベルクの弟子でありウェーベルンの盟友でもあるアルバン・ベルクは、新ウィーン楽派のひとりである。
ベルクは、ヴァイオリン奏者ルイス・クラスナーに協奏曲を委嘱されていたが、歌劇「ルル」を作曲中で、手つかずであった。
だが、一人の美しい娘の死をきっかけに、歌劇「ルル」を中断してこちらに取りかかった。
その娘とは、アルマ・マーラー(マーラーの未亡人)とヴァルター・グロピウス(バウハウス創立者)の子、マノンである。
ベルク夫妻はマノンを非常に可愛がっていたが、19才の若さで病に倒れる。
彼女の死を悼み、「ある天使の思い出に」と献辞を付し、レクイエムとしてヴァイオリン協奏曲を作曲した。
それから数ヶ月後の1935年12月24日、ベルク自身も病に倒れ、50才で生涯を閉じる。
12音技法を用いつつ、どこか調性的でもあるこの協奏曲が持つ雰囲気は、聴く者を非常に複雑な精神の世界へと引き込む。
冒頭の楽想に魂が乗っかれば、そこは「ある天使の思い出」の世界。
1楽章の前半はマノンの幼少時代のあどけない可愛らしさ、民謡をモティーフにした後半では彼女の過ごした楽しい日々が振り返られる。
2楽章はカデンツァ風に始まり、激しいヴァイオリンはマノンの病との闘い・苦しみを描き出す。
恐ろしい程の病魔と慟哭、そしてマノンの死、昇天。ここではバッハのカンタータのコラールが引用され、切な祈りと魂の浄化が奏でられる。
天使となったマノンを天へ導くコラール、この辺りからのカタルシスは言葉にならない。
最後は(メシアンの世の終わりのための四重奏曲でも似たようなことを書いたが)、天へ昇る魂を象徴するような、徐々に上昇し、響いてやまないヴァイオリンの調べ。
シンメトリックに冒頭の楽想が再び現れ、美しい娘の魂は小さな光となって消える。
「音楽は唯一の経験可能な死」というのが僕の持論だが、この曲は正に、聴く者を天国へと導く。
天使の思い出を持って、ベルク自身が、この曲を最後に天国へと向かったように。
 |
Berg: Violin Concerto Berg,Kremer,Davis,Bavarian Radio Symphony Polygram Records |
 Author: funapee(Twitter)
Author: funapee(Twitter)都内在住のクラシック音楽ファンです。コーヒーとお酒が好きな二児の父。趣味は音源収集とコンサートに行くこと、ときどきピアノ、シンセサイザー、ドラム演奏、作曲・編曲など。詳しくは→more