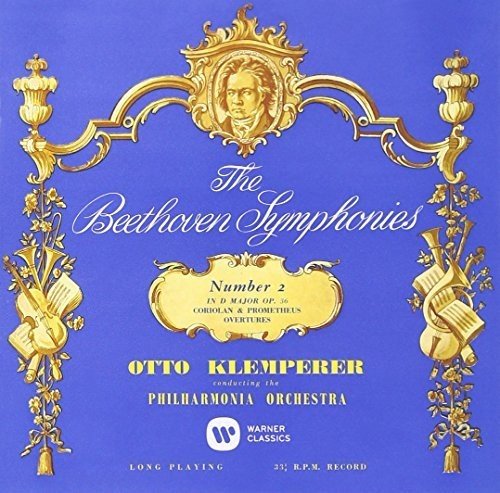ベートーヴェン ピアノソナタ第8番「悲愴」作品13
三大ピアノソナタの1つとして挙げられる第8番「悲愴」は、ベートーヴェン初期の傑作である。
1798年、彼が27歳のときの作品で、後期のようなベートーヴェンの音楽の深い森のような精神性はないが、それでもこの曲の魅力は後期の作品群と劣らない。
むしろ若かりし頃ならではのベートーヴェンの良さがある。
一般的な3楽章構成で、どの楽章も非常に有名だ。
特に2楽章の美しさと知名度は言うまでもないだろう。
モーツァルトのピアノソナタ第14番と構成や旋律がかなり似ているが、ベートーヴェンが意識したかどうかはわからないし、音楽の本質は全く別である。
「悲愴(原題 Grande sonate pathétique)」とは何だろうか。
これも交響曲第6番「田園」と同様に、ベートーヴェン自身が名づけた副題である。
少なくともわかるのは、ベートーヴェンの後期作品によくあるような、人間そのものを問うようなどこまでも深く沈み込む悲しみではないということだ。
作曲年代からも、そして実際に曲に触れれば尚のこと、もっと軽い悲しみであることがわかる。
まあ考えても答えなどないのだが、少し考えてみるのも悪くない。
冒頭、1楽章はグラーヴェの重々しい序奏から始まり、この序奏を基にしたソナタが形づくられている。
序奏から最初の主題へと移るところのなめらかさ、またグラーヴェからアレグロへの移行も印象深い。
特に1楽章は、単なる悲しみではなく、より嘆きに近いものなのだろうか。
2楽章の旋律の広がりを湛えた美しさからは、僕は静かな祈りや夜の水面といったイメージを抱くが、ふと「自分が受けた優しさ」かもしれないと思うこともある。
ここは何かしらの「悲愴」を持つこととなった原因のものなのだろう。この美しさこそ、悲愴を導いたと考えることにしている。
3楽章のロンドでメインとなる主題は1楽章のアレグロの第2主題と似ており、また2楽章の主題を修飾したような部分もあったりと、いかにも最終楽章らしい形をしている。
悲しみの中に若干きらびやかな雰囲気も無いわけではない。おそらくは、何かを想起しているのだろうし、そしてそれを思って再び嘆いているのだ。
標題音楽だが、ベートーヴェンはこの曲を作った後で「悲愴」と付けたという解釈が有力だ。
ベートーヴェンが抱いていた、若者らしい悩みや、若さゆえの苦悩、青春の苦悩からくる「悲愴」なのだろうか。
僕自身、それらを思って聴いてみると、この曲がいかに優れた芸術であるかよくわかる。
たとえばポップスは、自分の心を映してくれるような曲を好きになるものだ。
では、国も時代も離れたアーティストの、歌詞も無い楽曲はどうか。
こうして「青春時代の自分の気持ちにぴったり合う曲」がまたひとつ増える。音楽はいいものだ。
 |
ベートーヴェン:ピアノ・ソナタ「月光」「悲愴」「熱情」他 ヴラディーミル・ホロヴィッツ SMJ(SME)(M) |
 Author: funapee(Twitter)
Author: funapee(Twitter)都内在住のクラシック音楽ファンです。コーヒーとお酒が好きな二児の父。趣味は音源収集とコンサートに行くこと、ときどきピアノ、シンセサイザー、ドラム演奏、作曲・編曲など。詳しくは→more