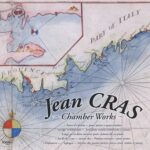ショーソン ピアノ三重奏曲 ト短調 作品3
僕がショーソンの音楽の特徴――何か不思議な心地よさのような感覚に包まれるのだが――について、どう表現したら良いものか思い悩んでいたとき、偶然ドビュッシーによるショーソンの音楽の批評の言葉に出会った。
それは以下のようなもので、僕のもやもやした感じを一蹴して、「そうそう、こういうことなんだよ!」とすっきり解決してくれたのである。ドビュッシーとショーソンの親交が深かった時期に、ドビュッシーは語っている。
“楽想が適切にドレスアップされていないのではないかと恐れるあまり、楽想に圧迫を与えるほどの重みを持たせてしまったために、それが自然に浮き立ってこない状態になっている”
これは特にショーソンの室内楽曲に言えることで、大体批判的なニュアンスなのだが、蓼食う虫も好きずきと言うもので、僕が特にショーソンの室内楽に魅了された理由、そしてショーソンの記事で連続して室内楽作品を取り上げた理由も、まさしくこれなのだ。
ショーソンの初期作品で、また初めての室内楽作品あり、1881年に作曲され、翌年初演された。
半音階を巧みに用いた旋律と循環形式の活用は、フランクの影響が大きい。
正直ドビュッシーの言葉を越えるほどに良い説明が出来るとは自分でも思っていない。
ショーソンが他のフランス作曲家と比較して一般的な人気が高まらないのは、一瞬聞くとまあ悪くはないのだが(そう、決して悪くはない、悪くないからこそ問題なのであって、悪いものというのは案外人気が出るものだ)驚くほど良いとも思えない、ということが往々にしてありうるからだ。
しかし、じっくりと聞き込むと、はじめは見えなかった「重みを持った楽想」が浮き立って来るかのように聞こえることに気づく。
特にこの曲の1楽章と3楽章はそういった体験に該当する。変化に富む旋律・強弱・調性と、スマートではなくむしろ着膨れしているかのような重みを感じる和音。暗く、鬱っぽい音楽を作り出すのには、このチェロのドッと来る低音と、ヴァイオリンの重音、ピアノの和音の多用が一役買っている。
トリオという構成上、耳が疲れるほどの重みではない。そして、その重みの中に聴く者が自由に飛び込んでいけるようになったとき、ショーソン独特の不思議に心地よい音楽体験を味わえるのだ。
この曲の魅力はそこだけではない。やや軽さのある2楽章の可愛らしさ、そして循環形式の使用が4楽章に与える絶妙な圧力。
濃密な重みと動きのある1楽章の旋律が、姿を変えながら現れ、終楽章は単純な美しさと複雑な美しさのバランスを保ちながら、思わず感嘆の声を唸らせるフィナーレ。圧巻だ。
このくらいの重みが万人にとって心地よいとは言い難い。しかし、それが心地よいと思う瞬間の僥倖は、ショーソンの数ある曲の中でもひとしおだ。
 |
Piano Trio Op 3 Ernest Chausson,Maurice Ravel,Pascal RogéOnyx Classics UK 売り上げランキング : 69186 |
 Author: funapee(Twitter)
Author: funapee(Twitter)都内在住のクラシック音楽ファンです。コーヒーとお酒が好きな二児の父。趣味は音源収集とコンサートに行くこと、ときどきピアノ、シンセサイザー、ドラム演奏、作曲・編曲など。詳しくは→more