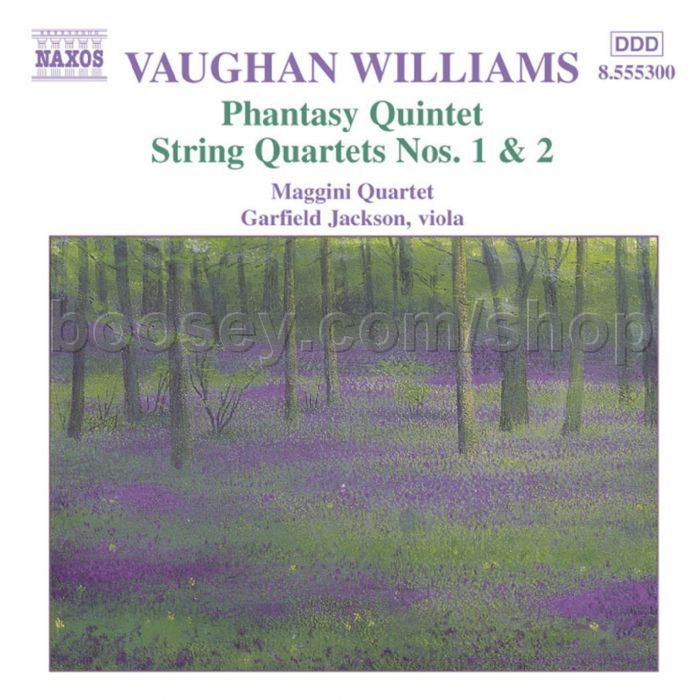ダンディ 弦楽四重奏曲第1番 ニ長調 作品35
ダンディの最も有名な作品「フランス山人の歌による交響曲」でブログを更新したのが2009年6月。それから8年半が経ち、さすがに僕自身のクラシック音楽の知識や文章力も多少はアップしているので、ここらでひとつ、ダンディの音楽の良さを世に知らしめるのに一役買ってやろうと思うのだ(なんか偉そうだなあ)。これで2017年のブログ更新は最後になるかしら。今回は弦楽四重奏曲第1番を取り上げよう。
ちなみに、ダンディの師匠であるフランクの弦楽四重奏曲については2012年に記事を書いた。書きたいことがなかなかコンパクトにまとまっていて良いと思う。段々と自分の中でハードルが上がってきて、一記事の文章量が増えていくのが、このブログの痛いところだ……。
フランクの弦楽四重奏曲がベートーヴェンへのオマージュならば、ダンディの第1カルテットはワーグナーへのオマージュと言っても良いかもしれない。もちろん、師フランクの影響は計り知れないが、交響詩ひとつ取ってみてもダンディの曲はフランクよりもワーグナー寄りだし、ダンディは弦楽四重奏曲を3曲作っているが、それらも加味するとやはりフランクよりもだいぶ聴衆を意識した作風の室内楽曲が多い。
何もフランクやダンディに限った話ではないが、19世紀後半のフランスで弦楽四重奏曲を作ろうという気概のある作曲家にとって、ベートーヴェンの壁というのは非常に大きかった。あえてベートーヴェンを意識しない作風のものはせいぜいグノーくらいかもしれない。しかしそのグノーの作品だって、死後になってから出版されたものなので、作曲当時グノーがどのような心境だったかは闇の中だ。後はベートーヴェンのカルテットを嫌って「古い聾者」と揶揄したフランスの大作曲家モーリス・ラヴェル様くらいか。
もう少し当時の状況を加えて話すと、国民音楽協会の存在もまた大きかった。サン=サーンスらが「ガリアの芸術」を旗印にフランス独自の音楽の創出を推し進め、多くの新作の演奏機会が増えた反面、ベートーヴェンをはじめドイツの伝統を意識した(いや、フランクやダンディらは国民性を超えた芸術を意識していたのだろうが)弦楽四重奏曲を作ろうとする者たちにとって、協会は少なからず壁として立ちはだかったに違いない。実際協会の中でサン=サーンスとフランクは対立する関係にあった。
そんな中で、はっきりとしたワーグナーへのリスペクトを感じられるカルテットを作ったダンディには賞賛を送りたい。1楽章の印象的な冒頭の4つの音は、クラシックが好きな人なら色々な曲が頭に浮かぶと思う。マーラーの第1交響曲(1888)の冒頭と同じだが、ダンディがこの曲を知っていたかどうかはわかりかねる。確実に言えるのは、ワーグナーの「パルジファル」(1882)の鐘の音であり、これはダンディもバイロイトに初演を見に行ったという記録があるので、知っていたのは間違いない。ダンディはリング(1876)の初演も行くほどのワーグナー好きである。
パルジファルの鐘の音は確かに印象的だ。なぜダンディはこれを選んだのだろう。答えはわからないけれど、手がかりになりそうな事柄としては、一つはドビュッシーが1885年から87年にかけた作曲した歌曲「忘れられたアリエッタ」の中の「木馬」という曲でこの鐘の主題をちょっと歪な形で借用しているのを見て「いや、僕の方が絶対いいのできるし」と思ったのではないか(※想像です)ということ、あるいはバレエ作曲家のドリーブがダンディによく言っていたという「パルジファルって良いよね、特に花の乙女たちのところ、可愛い子たちが舞台にいるってのはそれだけで良いわ」(※事実だそうです)という言葉に、怒りとやる気が燃えたのではないかということ、だろうか……。冗談っぽく書いたが、真面目なダンディのことだから当たらずといえども遠からずと思っている。幼い頃に母をなくし厳しい祖母に育てられたダンディは、バーナード・ショーっぽく言えば、愛国心と宗教と規範によって育てられたような人物である。
ダンディは39才(1890年)で弦楽四重奏曲第1番を書き上げた。例えば弦楽四重奏曲を手掛けた時期はフォーレが70代、師のフランクも60代だから、割と早い方である。ダンディは、自身が設立した音楽学校スコラ・カントルムで弦楽四重奏曲第2番について授業をしており、そのノートが残っているため、平行して作曲していた第1番についても参考にして良いだろう。古典的なソナタ形式を踏襲して、終楽章には舞曲風のロンド形式を置き、フランク・ファミリー伝家の宝刀、循環形式が作品全体に統一感をもたらす。なお第2番では、モーツァルトもジュピター交響曲で用いたバッハのフーガの転用について触れられており、やはりダンディのドイツへの視線ははっきりしている。
僕個人としては、1楽章の冒頭はシューベルトの「死と乙女」を彷彿とさせる。このD音の伸ばしはすぐにそちらへリンクしてしまう。重々しい荘厳で崇高な主題に、ふと一筋差し込む陽光のような柔らかな旋律の美しさ。「崇高」と「美」の対比というとカントを想起するが、やはりこの二項対立の概念は多くの作曲家にもインスピレーションを与えているだろう。二項対立を解決するようにソナタ形式は拡大を試みる。真面目に言えばそうなるがしかし、序奏から助走を付けて次の主題に入るところなんかは、ちょっとおどけたように聴こえて笑えてしまう。入ってしまえば濃厚な節回しの歌、あえて楽譜は載せないが、「ここでCisに落とすのがフランス臭さ!」と言えば、きっと伝わると思うのだが。
2楽章は緩徐楽章、1楽章の主題を別の風味で味付けして、期待を裏切らない循環形式だ。変ロ長調になって、この荘厳で崇高だったテーマが突如麗しく美しく奏でられるのだ。すぐに第1ヴァイオリンのソロがあるが、これはダンディの室内楽にしては非常にレアである。
3楽章のヴィオラの旋律はロシアの乳母の歌を彷彿とさせると指摘する人もいる。ダンディは楽章の頭に「流行歌のように」と書き記しているが、当時のパリではロシアの歌が流行っていたからありえない話ではない。またその後に現れるフレーズは、乳母が子ども相手におどけているような雰囲気がある。ダンディの過去を少しだけ思い起こしてみる。
4楽章は何から何まで包括的に提出するという、循環形式の極意と言おうか、あるいはシェイクスピアかはたまた第九の終楽章か。この小さな形式に大団円を詰め込もうとするのが僕は大好きだ。第1ヴァイオリンのレチタティーヴォから始まり、鐘のモチーフだけでなく序奏や他の1楽章からの要素も取り上げて、小さく展開していく。全国の循環形式ファン垂涎である。
1891年2月24日、イザイ弦楽四重奏団によってブリュッセルで初演され、4月4日にはパリの国民音楽協会でもサル・プレイエルでパリ初演された。定かではないが、ドビュッシーも会員だったから聴いていたかもしれない。1893年に作曲されたドビュッシーの弦楽四重奏曲は、全くアプローチは違うが、曲の最後の最後のフィニッシュだけは似ているのが面白い。
 |
String Quartets Ernest Chausson,Vincent D’Indy,Chilingirian Quartet Hyperion UK |
 Author: funapee(Twitter)
Author: funapee(Twitter)都内在住のクラシック音楽ファンです。コーヒーとお酒が好きな二児の父。趣味は音源収集とコンサートに行くこと、ときどきピアノ、シンセサイザー、ドラム演奏、作曲・編曲など。詳しくは→more