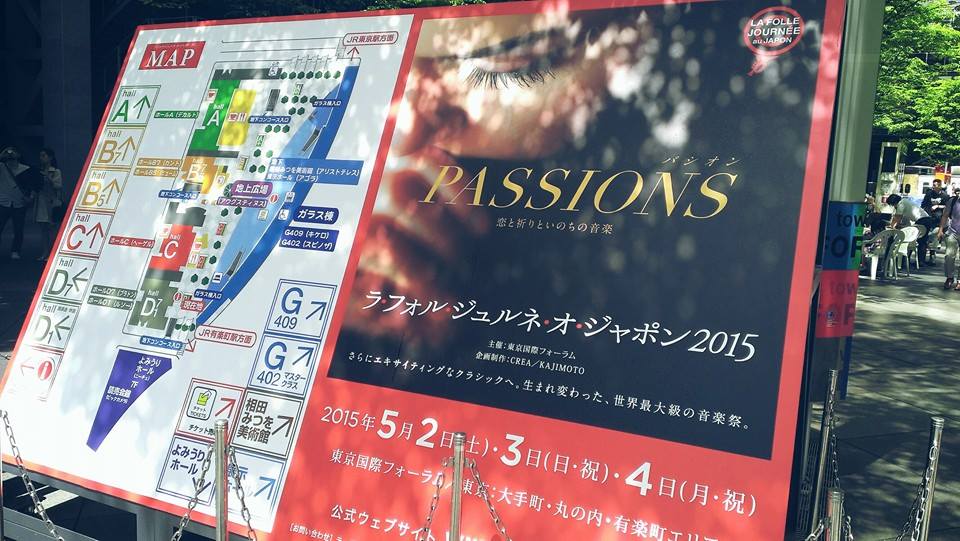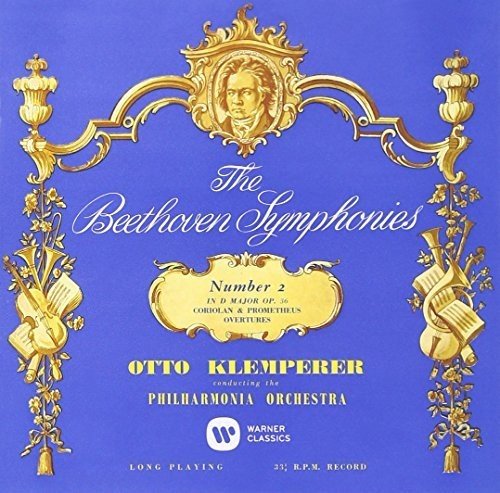ベートーヴェン ヴァイオリン ニ長調 作品61
ヴァイオリン奏者のレイ・チェンが2月頭にTwitterでチューリヒでの入国審査について書いて話題になっていた。「ヨーロッパでは何を?」と係員に尋ねられ、昨晩コンサートでしたと答えるチェン。すると相手は「何を演奏されたのですか?」と。ベートーヴェンのヴァイオリン協奏曲だと答えると、係員は何気ない口調で「何番?」と聞いてきたそうだ。一瞬言葉に詰まるチェンは「1つしかないです」(There’s only one)と答えると「結構です、お客様、お通りください」と。いやはや。
「ベートーヴェン唯一のヴァイオリン協奏曲」という言葉の重みだけで音楽にも随分箔がついたことだろうが、僕はこの曲を好きになるのにやや時間がかかった。ロマン派大好き人間にとって、また「皇帝」や「悲愴・熱情・月光」などからベートーヴェンを聴き始めた人間にとっては少し退屈だったから。それでも「これはベートーヴェン唯一のヴァイオリン協奏曲、良い曲に違いない、わからない自分が悪い」と自ら言い聞かせ、半ば洗脳して楽しめるようになった曲だ。
一目惚れみたいな熱い恋もいいだろうし、長年そこそこの付き合いを続けていたらいつの間にか愛が育まれたみたいなのでも、どっちでも良いよね。この曲は後者のパターン。今ではお気に入り曲に仲間入りだ。
でもやはり、何度でも言うが「ベートーヴェン」と「唯一」のブランド力の影響は絶対大きかったはず。もしベートーヴェンと知らなければ、あるいはベートーヴェンが3曲くらいヴァイオリン協奏曲を書いていたら、今のように流行もしなかったのではないか……などと言うとすぐ崇拝者から文句言われるから言わない。まあ、この仮定が無意味なのは確かで、なぜならこの曲から漂う強烈なベートーヴェン臭は「ベートーヴェンの作品かどうかわからない」なんて事態にはさせないことでしょう。さすが中期の「傑作の森」に該当する作品である。
もう少し言おう。ベートーヴェンの時代には、この曲は技術的に難曲で、しかもギリギリまで完成しなかったせいでリハなしで初演を務めることになったソリストのフランツ・クレメントは、1806年12月23日、持ち前の天才的な腕前で弾き切って大ブラボーを浴びたそうだが、その後の再演は少なかった。この曲の地位を高めるきっかけは1844年5月27日、ヨーゼフ・ヨアヒム12才のロンドンデビュー、メンデルスゾーンの指揮で演奏されたときだ。それまでこの曲は評価されておらず、ルイ・シュポーアも批判し、ある評論家は3流か4流作曲家の作品だと言い放ったそう。ヨアヒムは自作のカデンツァを用意して完璧な演奏を披露し、この曲の復活に一役買ったわけだが、やはりそれだけ難しいというか、昔から「誰が弾いても良い曲と思える」ような作品ではなかったのだ。
最近「精神性」について書いた記事と同じような話で、まさにメンデルスゾーンらによる巨匠の復権によって再び価値を与えられた曲である。もちろん単なる巨匠礼賛だけでなく、高い演奏技術と解釈の存在が大きかったのは上に書いた通りだ。
現代では様々な録音がよりどりみどり、たくさん選んでたくさん聴けば、きっと好きなものに出会えるはず。
1楽章冒頭のティンパニから千差万別だ。このティンパニをどう叩くか(あるいは叩かせるか)問題は非常に大きい。そもそもスコアには何の指示もないが、さてどうするか。クレッシェンドか、軽くアッチェルするか、強弱、テンポ、音色、たった四音の打楽器で聴かせるニュアンス。ティンパニスト、指揮者の意匠がすぐわかる。聴きどころが即あるのは嬉しい。
また、ソロの登場シーンというのが協奏曲、特にロマン派以降だと重要になるわけだが、この曲のソロ・ヴァイオリンの登場の仕方も相当やっかいである。まず出番までが長い。その長い序奏の19小節目の4拍目の8分音符2つにはスタッカートが付いているが、これをどうするかもまた問題(聴きどころ)。ここをアクセント気味にやりすぎると流れが途絶えるし、何もしないのも芸がないし、開始1分もしない間にオケと指揮者の方向性が読み取れると言ってもいい。
ソロは、例えばショパンのピアノ協奏曲第1番のように長々と待たせた上で印象的な主題でドーンと出るのでもなく、この曲ではヌルっと出る。しかも音も高い。こっちはこっちで難しそうだ。
2楽章はベートーヴェンの緩徐楽章らしい美しい旋律が特徴で、ソロの聞かせどころでもあり、上手い演奏で聴く分には最高だが、確かにこれを聴かせる技術を持たない演奏、例えば19世紀前半の演奏の多くはそうだったのだろう、それにはシュポーアが批判するのも肯ける。リズムという要素が溶けて消えてしまいメロディと少しのハーモニーだけが残ったようなスコアを美しく演奏するのは、当時であれば殊更、さぞ困難を極めたことだろう。
逆に3楽章はリズムが前面に出る。それは2楽章との完璧なコントラスト。それにしても3楽章の冒頭でグルーヴを作るのは、技術いかんではなく曲の所為で難しさがある。このいかにもベートーヴェンらしい舞踏性の粋とでもいうべき名フレーズは、ソロだけで入る上にオケ伴奏も非常に薄いこと、すぐにリットがあること、超高音で繰り返すことなど、この短いフレーズに幾多の試練が課されている。そして冒頭の出来が、その後の方向性を左右するのは言うまでもない。
それでも現代なら、19世紀よりはこの曲の魅力を引き出せる奏者は多いことだろう。事実、僕も実演でオリヴィエ・シャルリエやギル・シャハムの演奏に心から感服した。特にシャハムはヤンソンス指揮バイエルン放送響という強いバックもあり、それに負けない個性あるソロ、これは忘れがたい。
世の中には三大ヴァイオリン協奏曲とか四大とかの言い方もあって、ベートーヴェン、メンデルスゾーン、ブラームス、チャイコフスキーから任意の3つを選んで三大にするんだとか。
そういえば今挙げたのは皆ヴァイオリン協奏曲を1曲しか作っていない、オンリーワンだ。この中でポップなのはメンデルスゾーンとチャイコフスキー、渋いのはベートーヴェンとブラームスで、中でも最もシリアスで荘厳なのがベートーヴェンの協奏曲だというのが、長い間クラシック音楽ファンの共通認識だったと思う。
しかしこの曲は、20世紀における「楽聖による唯一無二の崇高な巨大建造物との対峙」のような演奏から、もっと愉快で時に荒々しいアレグロと安らかなラルゲットをどう楽しく聴かせようか、というような演奏が増えてきた気がする。オンリーワンの重みが名演を生むこともあっただろうが、今はその重圧から解き放たれ、新たな名演が生まれる時代になったのではないか。
Aparté (2010-10-20)
売り上げランキング: 295,352
 Author: funapee(Twitter)
Author: funapee(Twitter)都内在住のクラシック音楽ファンです。コーヒーとお酒が好きな二児の父。趣味は音源収集とコンサートに行くこと、ときどきピアノ、シンセサイザー、ドラム演奏、作曲・編曲など。詳しくは→more