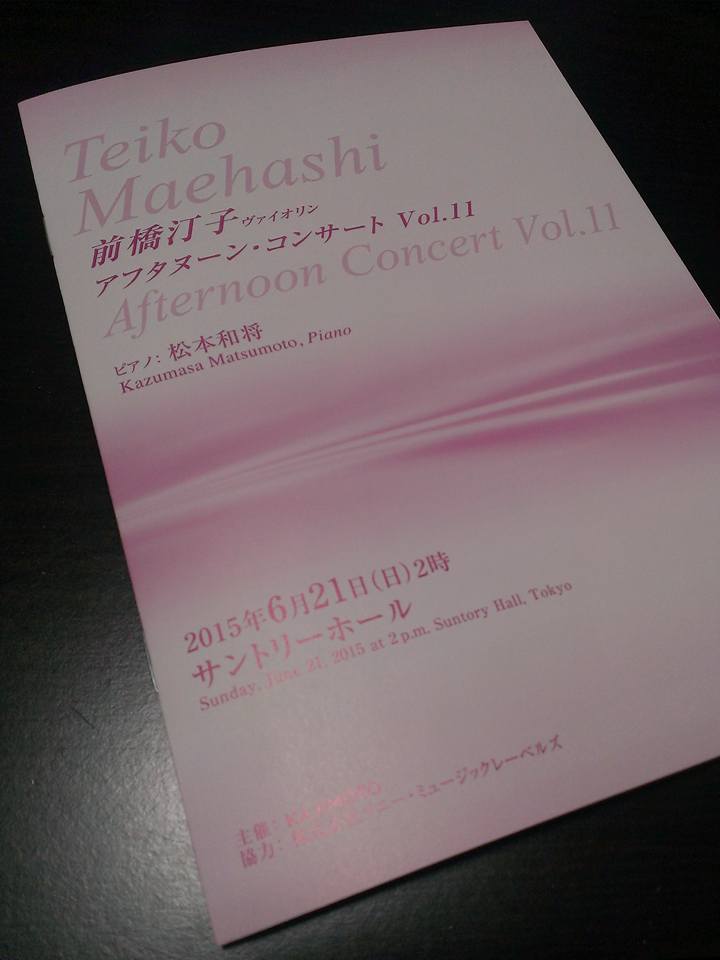アネ ヴァイオリン・ソナタ第5番 ハ長調 作品1-5
バッハのことを「音楽の父」と呼ぶことがある。ハイドンは「交響曲の父」、ヘンデルは「音楽の母」と言うこともあるらしい。本当か? なんでヘンデルは母なんだ。こういう二つ名は面白いけど、親しみを込めて呼ぶ良い面と、変な誤解を生む悪い面と両方あることを認識しなければならない。
今回取り上げたい作曲家はフランス・バロックのヴァイオリニスト、作曲家、ジャン=ジャック=バティスト・アネ(1676-1755)である。もう何を言うか想像できると思うが、彼のことを「フランス音楽の姉」と呼ぶのはどうだろう。アネは男だけど。ヘンデルも男なのに母だな、良いのか? 良くないな!
フランス・バロックのヴァイオリニストというと、ジャン=マリー・ルクレール(1697-1764)が有名だ。アネはルクレールよりも20歳近く年上になる。だいぶ年の離れた姉、じゃなくてアネ。ルクレールはイタリア流のヴァイオリン奏法をフランスに持ち込んだ第一人者のような扱いを長年されてきたが、最近は研究も進み、ルクレール以前にもそのようなフランスのヴァイオリニストたちがいるのだと、再発見されるようになってきた。その一人が、今回の主役アネである。昔、何かのCDの解説でルクレールを「フランスのバッハ」と称えているのを読んだ。となると、ルクレールは「フランスの音楽の父」だから、それより年長のアネは「フランスの音楽の父の姉」つまり「フランス音楽の伯母」ということに……良いのか? 良くないな!

冗談はこのくらいにしよう。別に僕はフランス・バロックのヴァイオリニストを詳しく追い求めていたのではなくて、単にこの変わった音盤ジャケットに惹かれて聴いただけである。この魚は調べたらマトウダイという魚で、フランスではサンピエールと呼ばれており、フランス料理ではムニエルなどで食べる定番らしい。フランス繋がりでこのジャケットなのかな、レーベルはHungarotonだけど。美味しい音楽なのは確かだ。

アネはパリで生まれ、父からヴァイオリンの手ほどきを受ける。父はジャン=バティスト・リュリ(1632-1687, リュリこそ本当のフランスバロックの父だ)の弟子で、宮廷の弦楽合奏団「フランス王の24のヴィオロン」の一員であった。子アネは父から学んだ後、ローマで4年間コレッリに師事。コレッリはアネの腕前に感激し、自分の弓をアネに渡したそうだ。1701年にはルイ14世の前で演奏。ルイ14世はリュリをお抱えにしてフランス独自の音楽を追い求めた王だが、アネの演奏したイタリア音楽を絶賛した。なおこのときはアントワーヌ・フォルクレ(1671-1745)のヴィオールと、フランソワ・クープラン(1668-1733)のクラヴサンが伴奏を務めたとのこと。アネも後に「24のヴィオロン」に加わり演奏している。
ヴァイオリンのためのソナタ作品としては1724年の曲集(Op.1)と1729年の曲集(Op.3)があり、前者はややイタリア風が色濃く、イタリア語表記のタイトルやテンポ表示が多くなっており、後者はフランス語表記が増え、音楽もフランス風が強くなっている。
何がどうイタリア風、フランス風なのかというのは難しいが(だったら使うなという話だが)、17世紀のフランスにおいて、ヴァイオリンはイタリアほど重要な楽器ではなかった、という差がある。無論フランスでもオーケストラや室内楽で大いに使われていたが、超絶技巧で魅了するようなスタイルは広まっていなかった。フランスの音楽家から見て、イタリアのヴァイオリン音楽は過激、奇抜、劇的過ぎるという印象だったようで、フランスはもっと穏やかで優雅で美しい均整の取れた音楽である、という考えが一般的だった。まるで現代のファッションブランドの話をしているみたいだ。17世紀も終わりに近づき、リュリの影響力が小さくなるにつれて徐々にイタリアで流行っているヴァイオリン音楽がフランスでも受け入れられるようになっていった。ルクレールがその最たるところ、ということだろうが、アネが活躍したのは過渡期である。いずれにせよバロックの頃にはこういう奏者兼作曲家が数え切れないほどいたのだろう。例えば、最近ではジャン=バティスト・スナイエ(1688-1730)の録音があったが、スナイエはアネとルクレールの間くらいの世代のヴァイオリン奏者で、ソナタ集や、ルクレール作品と併録した音盤(↓)などがある。こうした歴史の隙間を埋める作業が増えてくるのは嬉しいことだ。

“Générations” Senaillé & Leclair : Sonatas for Violin and Harpsichord
Théotime Langlois de Swarte & William Christie
今回はアネのソナタ第5番、ソナタ曲集第1巻(Op.1)の5曲目にあたるハ長調のソナタを挙げてみた。先の通りで言えばイタリア風が強い方にあたるが、この3楽章からなるソナタは、最後の3楽章にLes Forjerons(鍛冶屋)と副題がある。素早いパッセージが続き、技巧的に魅せる曲と言って良いだろう。こうしたものがフランスに入ってきたばかりの頃、と考えながら聴くと、楽しさもまた一段と増す。
しかしそれだけではなく、1楽章のAndanteは優雅で美しいメロディーが楽しめるし、2楽章Allegroは多少メカニカルではあるが、ひけらかすほど技巧的ではない。いい塩梅でイタリア風を取り入れたソナタである。他のソナタは楽章数が多いものや舞曲があるものなど違っており、様々に楽しめる。
フランスの著述家、ノエル=アントワーヌ・プルーシェ(1688-1761)は、アネについて次のように言及している。
「バティスト氏は、あらゆる種類の困難を貪るような野心を良しとしない。演奏が驚異的と思われる曲には何の施しも与えず、聴き手を確実に喜ばせる曲を最も高く評価する」
「この観点で言えば、楽器の音がつながり、持続し、まろやかで、情熱的で、人間の声に合致していることが要求される。人間の声の模倣と補助に過ぎない。ドイツもイタリアもイギリスも、彼にとっては全て同じだ」
最近似たようなことをブログに書いたなと、思い出すのはタルティーニである。激しい技巧や過度な演劇性を避け、自然の模倣を追い求めたタルティーニ。タルティーニは1692年生まれだから、ルクレールに近い世代だ。ルクレールもまた、ある作品の冒頭に「重要なのは、声楽作品や表現豊かな作品に人々が加える音符の混乱、見栄えを悪くするだけの音符の混乱を避けることだ」と書いた。
イタリア流の激しいヴァイオリン、これだってまだまだ未知の作品が沢山あるのだろう。イタリア・バロックも初期のヴァイオリン作品を聴くと、まさに黎明期、キレキレにキレ散らかしてる尖った作品があって、奇抜で激しい音楽の宝庫である。以前ストラヴィンスキーがヴィヴァルディを批判した件についてブログに書いたが、そうした音楽こそストラヴィンスキーの惹かれた音楽でもあり、それらが徐々にイタリア国内でも落ち着いていって、フランスではもっと円やかに折衷しながら発展していった。
アネのソナタはまさにその折衷の好例である。こうした音楽が聴けるようになるのは幸せなことだ。
 Author: funapee(Twitter)
Author: funapee(Twitter)都内在住のクラシック音楽ファンです。コーヒーとお酒が好きな二児の父。趣味は音源収集とコンサートに行くこと、ときどきピアノ、シンセサイザー、ドラム演奏、作曲・編曲など。詳しくは→more