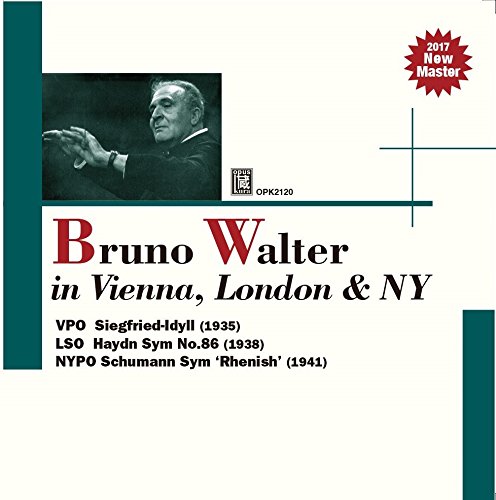シューマン 交響曲第1番変ロ長調 作品38「春」
シューマンの交響曲というと、そのオーケストレーションの弱さが常に指摘され続けてきたことは周知の事実である。
昔はシューマンの交響曲をいかに指揮者が改めるか、という点に注目がいったのだが、最近は楽譜通りに演奏するようにはなっている。
しかし、結局は良い演奏をするためにパート間のバランスやハーモニーを整える努力を要するわけで、彼の「管弦楽法の弱さ」は現代でもほぼ変わらないだろう。
それでも当時、「交響曲を書く」というのは、一流の作曲家としてのステータスでもあった。
妻クララの薦めもあり、シューマンは交響曲を作ることになる。
クララとの結婚の翌年である1841年、シューマンは初めての交響曲「春」を完成させる。
初演のリハーサルの際、指揮者のメンデルスゾーンから非常に初歩的な管弦楽法のミスを指摘され、シューマンが赤面するということもあったようだ。
しかし、初演は成功で好評を博し、シューマンは管弦楽曲への自信を徐々に付けていくことになる。
第1番「春」は、その名の通り春の始まりとその様子が描かれているような印象である。
シューマンの躁鬱が作品に現れる曲は数多くあるが、あまり強くそれを感じることもなく、シューマンにしては非常に爽やかな作品である。
ファンファーレに導かれ、「春」が地の底から湧き上がるようなような1楽章の第一主題は、最も季節を感じるところである。
2楽章の弦による旋律も、哀愁を帯びつつもぬくもりを感じる、シューマンお得意のロマンチックな魅力がある。
3楽章に現れる、喜びに体がうずくような、でもまだ我慢しているような、そんな雰囲気が僕はたまらなく好きである。
そして4楽章で春はたけなわを迎え、その喜びは美しく開花するのだ。
僕はこの曲をよく好んで聴くのだが、時々思うことは、これは交響曲である必要があったのだろうか、ということだ。
管弦楽法の弱さは確かにある、しかし、うららかな春の様子や、我々の心を揺さぶる美しい「うた」がこの曲の最大の魅力なのだ。
彼の音楽のアイデンティティは、旋律(もっと言えば音と音の繋がり)にどこまでも深い「ひとの心」があるところに思う。
それが我々の心に情感を与えるのが、たまたま管弦楽だっただけの話である。
もちろんシューマンに限った話だが、彼の交響曲が愛されてきた理由もこれとそう遠いものではないだろう。
彼は作曲家としてはそういう意味での天才であり、まただからこそ僕の最も好きな作曲家なのである。
 |
Symphonies 1 – 4 Robert Schumann,David Zinman,Zurich Tonhalle Orchestra Arte Nova Records |
 Author: funapee(Twitter)
Author: funapee(Twitter)都内在住のクラシック音楽ファンです。コーヒーとお酒が好きな二児の父。趣味は音源収集とコンサートに行くこと、ときどきピアノ、シンセサイザー、ドラム演奏、作曲・編曲など。詳しくは→more