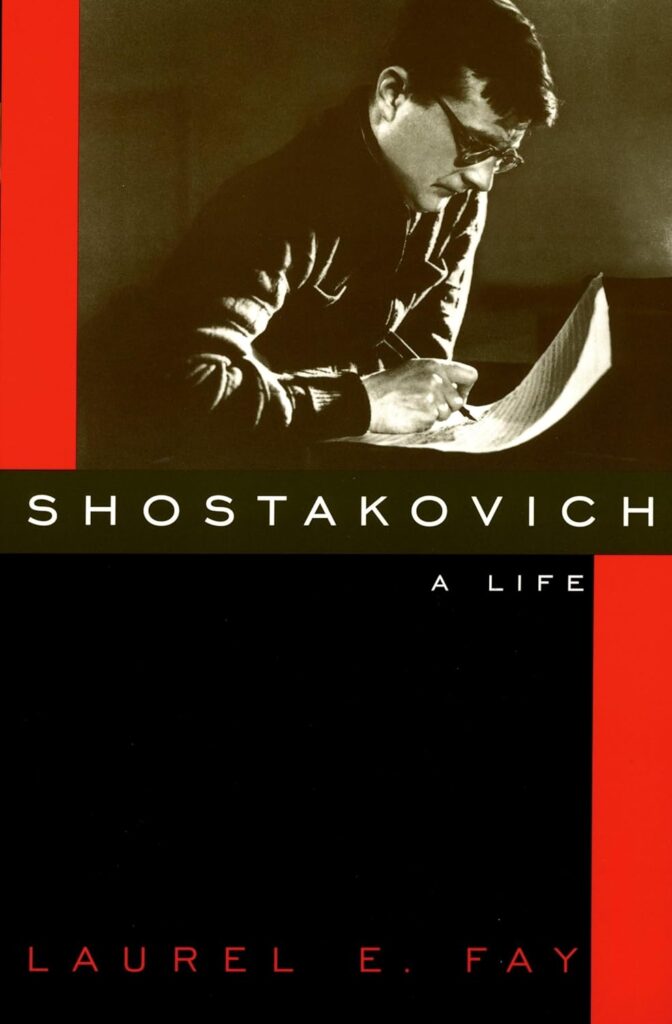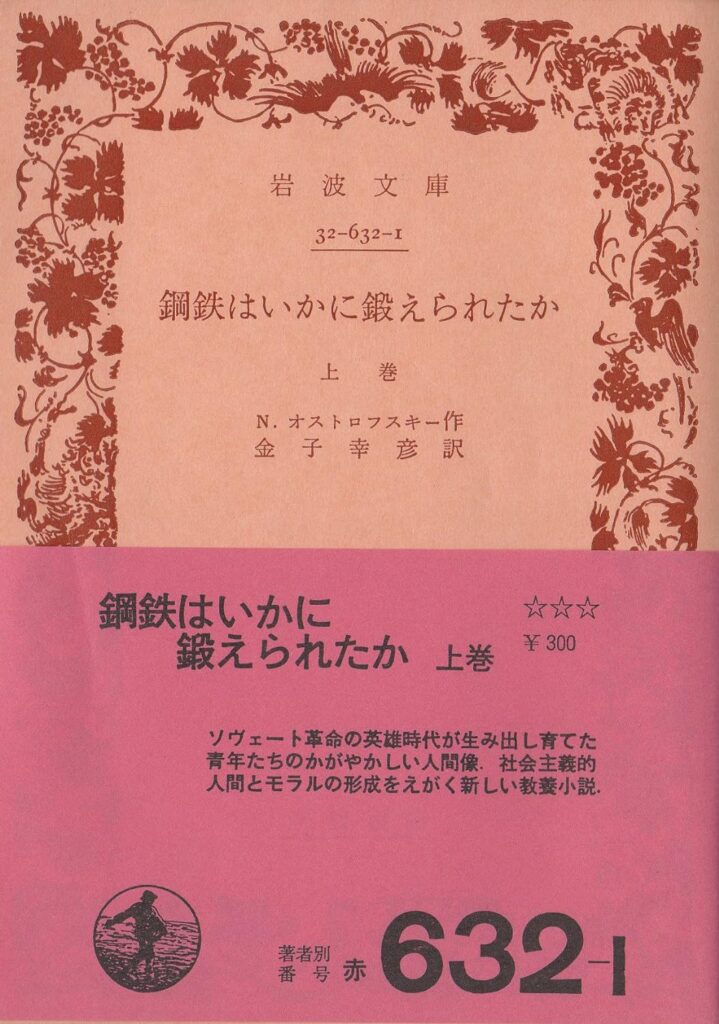――2022年8月9日、ショスタコーヴィチの命日(1975年8月9日)に寄せて
2年前、2020年4月に書いた「精神性」に関する記事の中で、2011年の東日本大震災のときのことを振り返っている。その部分を抜粋してみよう。
僕は3.11の数日後、東京から金沢へ向かう夜行バスに乗っていた。友人に会うのと、チェコ・フィルの来日公演に向かうためだ。結局公演はキャンセルになってしまい、吹雪の金沢で映画館に行ったのを思い出すが、それはともかく、原発がどうなるかという混乱した社会状況の中、夜行バスでひとり聴いたコバケン指揮チェコ・フィルのマーラー「復活」は今でもよく覚えている。あるいはその翌月、仲間内で一緒に聴いたショルティ指揮シカゴ響の「復活」も。この曲のこの盤を提案したのは福島の方だった。
こうしたことを振り返ろうと思うに至ったきっかけというのが、新型コロナウイルスの流行である。また精神性なるものについて何か書いておきたいと思うに至ったのもそうだ。僕は忘れっぽいというか記憶力に自信がなく、なるべくライフログを付けるようにしており、それを見返した際に上のマーラーの話に加えてもう1つ「3.11とクラシック音楽」に関連する内容で「ああ、そうだったな」と、当時のことを噛みしめるようなものがある。それもいつかブログに書こうと思っていた。2022年になって、やはり今年書いておこうと思うに至ったのは、ロシアとウクライナの戦争がきっかけである。
2011年、今から11年も前となると、当然僕も若くて(今でもハートは永遠の17歳だけど)、とにかく、めちゃくちゃたくさん音楽を聴きまくっていた時期でもある。元々寝付きが悪いのもあり、深夜からオペラのDVDを見出したり、バッハのマタイとか長い曲を鑑賞しだしたり、朝までひとりブルックナーチクルスしたり、そういうことをして悦に入っていた訳だが、2011年3月11日は、「午前」3時に、ショスタコーヴィチの交響曲第14番「死者の歌」を聴いていたとメモに残っている。3月11日の午前3時、午後ではない、午前3時だ。演奏は、ロストロポーヴィチ指揮モスクワ・フィル、ガリーナ・ヴィシネフスカヤ(S)、マルク・レシェティン(B)の1973年録音。先に挙げたマーラーの復活は聴いたことをよく覚えているが、ショスタコーヴィチを聴いていたのは、昨年自分でメモを見返すまで聴いていたことをすっかり忘れていた。
1969年に完成したショスタコーヴィチの交響曲第14番は、作曲者が「死」を意識した時期の作品である。7年前の1962年に、ショスタコーヴィチがロシアで最も偉大な作曲家だと信じているムソルグスキーの歌曲集「死の歌と踊り」を管弦楽用に編曲をしたときから、自身も「愛と死」をテーマにした音楽を作りたいと考えるようになったそうだ。1969年1月、病気で入院していたショスタコーヴィチは、インフルエンザ(いわゆる香港かぜ)の流行のため誰もお見舞いに来られず、孤独の中で作曲を続け、2月にはピアノスコアが完成し、オーケストレーションは2週間で完了。もしかすると、死への恐怖が駆り立てたのだろうか……などと思いつつ、震災から10年後にあたる2021年の3月11日にも、再びこの演奏を聴いた。流行り病で人とも会えないのも、当時のショスタコーヴィチの状況と似ているな、なんてことも思ったり。
ショスタコーヴィチが交響曲第14番「死者の歌」初演時にスピーチをしたということは、日本語のWikipediaにもあるように、まあまあよく知られている話だ。ただ、案外インターネット上では詳しく日本語で書かれたものが見当たらない。この話に関するソースは色々あると思うが、とりあえずLaurel E. Fayの“Shostakovich: A Life”などを参考に、意訳して書き出してみよう。ショスタコーヴィチはスピーチの際にある小説の一節を聴衆に語っており、冒頭の部分をショスタコーヴィチの名言のように扱っている記述も見られるが、実際はショスタコーヴィチのオリジナルではない。その小説については後で紹介する。
「人生は人間の最も大切な財産です。人生は一度しかない。だから私たちは、人生において誠実に、胸を張り恥じることなく生きるべきなのです。目的なく過ごした年月を思って胸が苦しくなったり、卑小で不名誉な過去を恥じたりすることなく生きるのです。そうして生きて、死の瞬間には、人間性の解放のために戦うという世界で最も崇高な目的に、自分の人生と自分のエネルギーのすべてを捧げたと、そう言えるように生きなければなりません。この交響曲を聴く人には、人生が本当に美しいものであることを実感してほしいと思います。私の交響曲は、死に対する熱烈な抗議であり、誠実に、良心的に、高貴に生きるべきであり、決して卑劣な行為をしてはならないということを、生きている人に思い出させるものです。これは非常に重要なことです。死は全ての人に待ち受けており、人生の終わりということに私は何の意味も見い出せません。死は恐ろしいものです。その先は何もない」
死は人生の終わりで、そこに意味はない……ショスタコーヴィチは「死は新しい世界の輝かしい始まり」というような考え方を拒絶し、また死を美しく恍惚とした音楽で表現する作曲家たちとは正反対の意見を音楽で表現したのだ。もう少し引いて見ると、意味はないというよりも、ショスタコーヴィチは「死は本当の本当に終わりである」ということ自体を一種のインスピレーションとして、自分の芸術家人生を全うしようとしたのだも捉えられる。例えばソクラテスは「死や死後の世界のことを知る者は誰もいないのに、死を最大の悪と恐れるのはおかしい、だからこそそれを恐れて悪く生きてはいけない」というような哲学があると思うが、ショスタコーヴィチには「死は終わりそのものである、だからこそ善く生きなければならない」という哲学があるように思われる。ショスタコーヴィチがそのような信条を抱くのも、当時のソビエト連邦のことを考えてみれば、想像に難くない。
少し話は逸れるが、僕はブログでもTwitterでもよく話題にするように、ロシアとイタリアの音楽がここ十年弱の興味の中心であり、特にロシアの知られざる放送音源は相当数録音したので、時々そういう話題もする。何はともあれ、明快で濃厚なロマンティック音楽が好きなのだ。僕は自分があまり鋭敏で繊細なタイプでないことは自覚しており、大雑把で適当だけど(おおらかとも言う)、それでも何か熱い気持ちはあって、なんというか、ロシアとかイタリアの音楽はとても肌に合う。両国とも音楽以外のことについてはそれほど詳しくはないにせよ、まあそれなりには知っているつもりだっただけに、ロシアのウクライナ侵攻はショックだった。というか、危うい関係だとは知っていながらも、こうなることを予見すらしていなかった自分がショックでもあった。音楽ばっかり聴いているだけで、自分は何もわかっていないんだなと突きつけられたような気持ちだった。
ロシアの音楽は変わらず大好きだが、それをウキウキしながら語ろうと思う頻度そのものは減ってしまった。インターネットを見れば、よくわかっているのか、わかっていないのか、どうなのか知る由もないが、様々な音楽ファンがロシアとウクライナの戦争について持論を展開している。僕はよく知りもしないことを素人の分際で偉そうに言いたくないと思いつつも、この事態に対して自分は一体何ができるのだろうか、この件について何を語ることができるのだろうかと、ぼんやり思っていた。政治にも戦争にも詳しくないし、金も時間も才能もない。でも、自前のブログを持っていて、音楽の知識だけはちょっとはある方だ。そして、このショスタコーヴィチの交響曲第14番には、ロシア(ソ連)だけでなく、ウクライナも大いに関わっているということを知っている。さあ、話を続けよう。
ショスタコーヴィチの交響曲第14番の肝とも言える第10楽章「詩人の死」は、死はすべての終わりだということを、最も強く訴えている楽章だと思う。――果実が腐っていくように、詩人は死んだ……死は芸術の終わりであり、芸術家が描く世界の終わりである――この楽章はライナー・マリア・リルケ(1875-1926)の詩を使用した楽章であり、ショスタコーヴィチの初演時のスピーチと重なる内容もある。この曲を愛好する人のどれほどの人が、リルケが「詩人の死」(『新詩集』より)を書いたきっかけを知っているだろうか。リルケとロシア文学の関わりの大きさは周知の通りだが、この詩人の死は、彼がウクライナのキエフで、ウクライナの詩人タラス・シェフチェンコ(1814-1861)のデスマスクを見たことが創作のきっかけとなっている。近代ウクライナ語文学の祖であり、ウクライナの農奴の解放に力を尽くしたシェフチェンコ。今もなお、ウクライナの人々にとっては英雄であり、民族のアイデンティティの源でもある。その死に顔から、リルケは霊感を得たのだ。ショスタコーヴィチの音楽で「彼はかつて世界のすべてを知っていたが、その知識は次第に消え、再び無関心の日に引き戻された」とリルケのそうした詩が歌われるのを、今となっては聴衆はどう聴くだろう。

上述した通り、交響曲第14番の初演時にショスタコーヴィチがスピーチした内容はある小説から借りたものと書いたが、その小説というのも、ウクライナで生まれた作家、ニコライ・オストロフスキー(1904‐1936)の『鋼鉄はいかに鍛えられたか』である。これは彼の代表作でありまた半自伝的小説で、全身麻痺や失明といった困難に打ち克って書いた小説だ。岩波のコピーを引用すると、「ロシア革命の吹きすさぶ嵐のなかで,古い力の破壊と新しい社会の建設のために,ヒロイズムと献身の熱情にもえつつ,たたかい,傷つき,あるいは倒れていった青年たちの輝かしい人間像を描く.歴史の転換の巨大なうずまきのなかでいかに生き,かつ闘うべきかの手本を示したといわれる感動にみちたオストロフスキー(1904‐1936)の自伝的小説.」とある。体制に対して好意的になる若者を多く生み出した古典という評価もある社会主義リアリズムの作品であり、ソビエト連邦がウクライナに与えた影響というものを嫌でも実感できると思う。そうであっても、読めばおそらく、彼が体制について本当はどのような態度であったかも、想像できてしまうに違いない。それは我々がショスタコーヴィチの音楽を聴いたときと同じように、だ。だからこそ、そういう世界で生きている音楽家だからこそ、彼は初演時にオストロフスキーの小節から抜粋してスピーチしたのだろう。ぜひ、そんなことも踏まえて、上述のスピーチを再度読んでほしい。
これらの話をもって、今のロシアとウクライナがどうこう、と言うつもりはない。僕にできることは、これらの事実をここに書き記すことだけである。ショスタコーヴィチが強く訴える、「偉大な芸術家も、死んだら終わり」というのは、そんな風に思いたくもないが、それはそれで、やはり事実である。それ以上の作品は生まれないし、忘れ去られていくこともある。しかし、死んでしまった芸術家に対して、今、生きている我々にもできることがあるというのもまた事実だ。僕は芸術家でもなければ音楽学者でもなく、ただの一愛好家に過ぎないが、それでもショスタコーヴィチよりも優れていることがあると言える。それは「今こうして生きている」という一点についてだ。そんなことを自慢してどうするのかと、何も知らない人からは鼻で笑われるかもしれないが、ショスタコーヴィチには「そんなこと」が全てであったと、そう思わざるにはいられない。きっと天国のショスタコーヴィチも肯定してくれるんじゃないかだろうか。僕は今、生きて、ショスタコーヴィチの音楽の話をしている。何も僕だけではない、あなたも、あなたも、あなたも。
そういえば同じ14番繋がりで思い出したが、僕はシューベルトの弦楽四重奏曲第14番「死と乙女」が大好きで、ブログ記事も書いているし、珍しく音盤紹介記事も書いている。病に冒され、絶望の内に書いたとされるこの曲も、命を削ってでも輝こうと、必死に生を全うしようと、そんな風に思えて、ブログに書きたくなったのだ。2011年の午前3時、僕は多分、特に何も考えずショスタコーヴィチの交響曲第14番を聴いていたはずだ。それだって、生きているから聴くことができていたのだ。その12時間後には、多くの人が命を落とす未曾有の災害が起こるなんて思いも寄らない。幸運なことに、僕はまだ生きている。あれから11年も経った。僕もその頃より少しは音楽に詳しくなったので、こうして書いてみたというわけだ。今日も音楽を聴いて、それについて何か言えるのは、今僕が生きているからである。それだけは事実、いや真実のはずだ。
【参考】
Fay, L.E., Shostakovich: A Life, Oxford University Press, 2005.
Hlukhovych, A., “…wie ein dunkler Sprung durch eine helle Tasse…” Rainer Maria Rilkes Poetik des Blinden. Eine ukrainische Spur, Königshausen & Neumann, 2007.
 Author: funapee(Twitter)
Author: funapee(Twitter)都内在住のクラシック音楽ファンです。コーヒーとお酒が好きな二児の父。趣味は音源収集とコンサートに行くこと、ときどきピアノ、シンセサイザー、ドラム演奏、作曲・編曲など。詳しくは→more