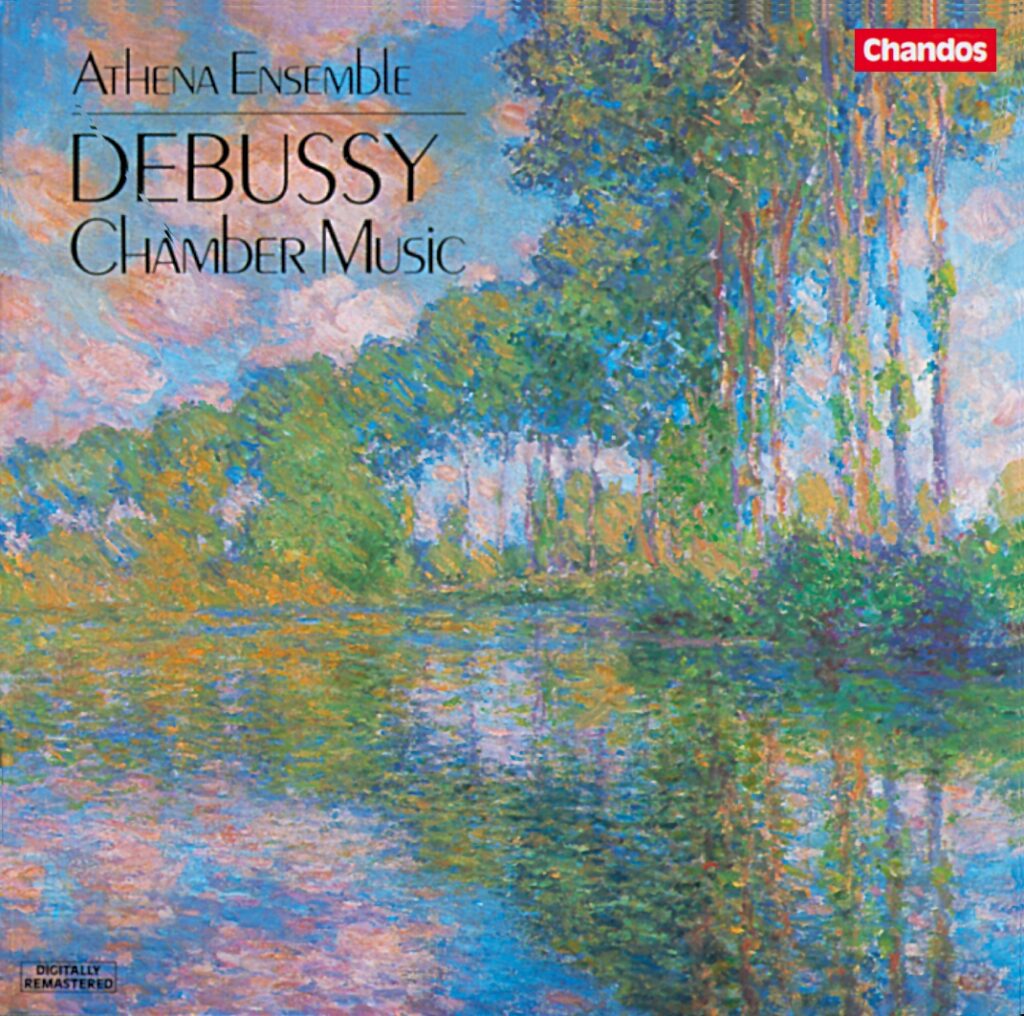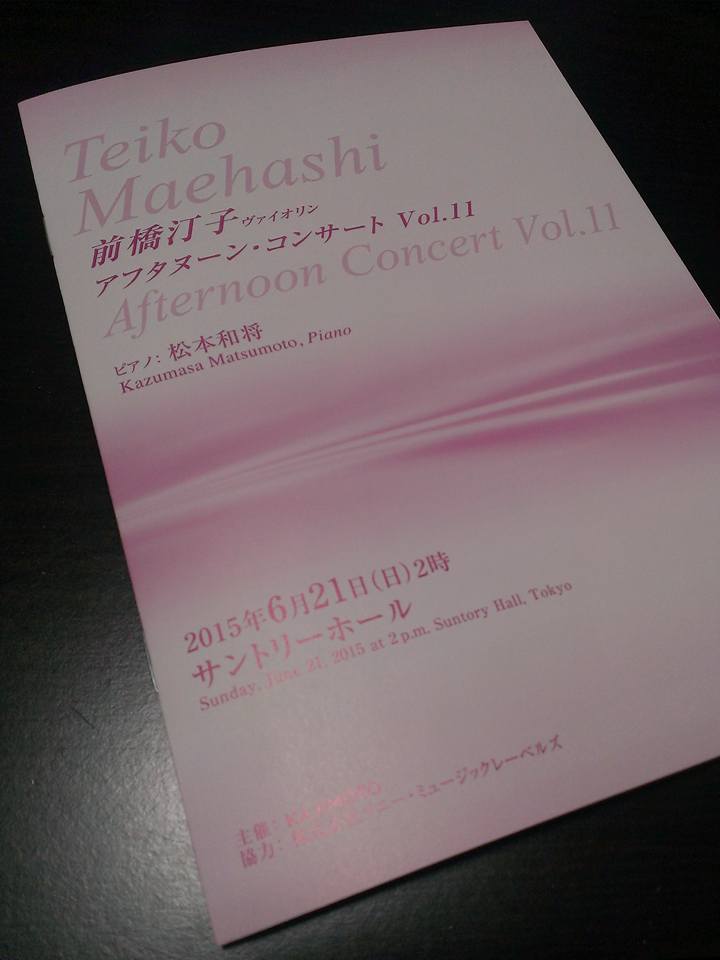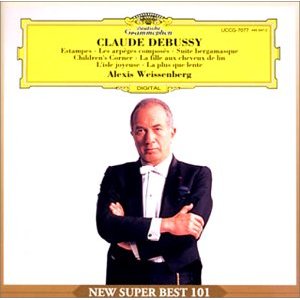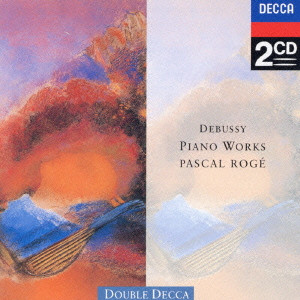ドビュッシー ヴァイオリン・ソナタ
東京・春・音楽祭という素敵なイベントがある。2024年は20周年だったそうだ。僕が初めて行ったのは確か2010年で、東京都美術館のボルゲーゼ美術館展記念コンサートと、京都フランス音楽アカデミー特別演奏会に行ったのだった。それからも毎年ではないが、行けるときはたまに行って楽しんでいる。今年は東京都美術館の印象派展記念コンサートがあり、ドビュッシーのヴァイオリン・ソナタを聴くことができた。僕はドビュッシーならだいたい何でも好きだけど、このヴァイオリン・ソナタも大好きな曲の一つ。第一次世界大戦中の1916年から1917年にかけて作曲された、ドビュッシーの最後の作品である。
晩年のドビュッシーは病に冒され、身体の調子も思わしくなく、友人のアーサー・ハートマンと行く予定にしていたアメリカ旅行をキャンセル。旅行に行かなかったからこそこの曲が世に生み出されたのだと考えると、後世のファンとしてはドビュッシーの決断に感謝するほかない。もはや自分は「歩く死体」であり「病人が戦時中に何を作曲できるかのドキュメンタリーだ」という旨の皮肉っぽい内容を手紙に残している。
1917年にガストン・プーレ(東京藝大の客員教授も務めたジェラール・プーレの父)とドビュッシー自身のピアノで初演。戦争負傷者の保養施設のためのチャリティコンサートだった。結果的には病人が戦時中にできることとしては十二分なほどに徳の高い行いとなったもの、なんだか不思議な話。
3楽章構成で1楽章Allegro vivo、2楽章Intermède: Fantasque et léger、3楽章がFinale: Très animé、全体で13分ほどの長さ。いわゆる楽曲解説は、有名作品なのでネット上に溢れているだろうから詳しくはそちらを参照してください。
ピアノに導かれて始まる1楽章のヴァイオリンのフレーズ、まるで人を慰めるような、優しく哀愁あるフレーズはきっと負傷者の心にも響いたことだろう。もちろん「慰めるような」と考えたのは僕の勝手な解釈だが、淡い色合いと穏やかで温もりある旋律は、聴く者を突き放すような孤高なものではなく、もっと身近に寄り添うタイプのものだ。これを書いている今は雨が降っているが、雨降りの日にも合うし、柔らかな日差しにも合う音楽。春にもいい、秋にもいい。夏は……最近の日本の夏は暑すぎるので合わないかもしれない、でも冷房の効いた涼しい部屋に響かせるのも抜群に良さそうだし、冬に暖かい室内で聴くのだってたまらないだろう。
2楽章、スケルツォ風の気まぐれな表情も素敵で、またいきなり内省的な雰囲気を醸し出す瞬間があるのも面白い。まるで一枚の絵画を鑑賞しているかのようだ。あちらでは少女が蝶を追い、こちらでは老人が静かに腰掛けている。それも全てぼやけている、強さや激しさも、描かれるもの全ては儚さを纏っていて、ゆらりと漂うハーモニー。
ドビュッシーはこの曲について「騒々しい喜びに満ちている」と語ったそうだが、確かに3楽章は喜びに満ちて終わる。楽章の冒頭では主題が回帰して、まるでフランクだ。4年前に書いたドビュッシーの弦楽四重奏曲のブログ記事もどうぞ。この楽章はジプシー音楽の影響や、タランテラのような雰囲気があるとよく指摘される。そういう要素の持つ楽しさもあるが、楽しさや喜びと同時に、悲しさも感じられる音楽だ。光と影、喜びと悲しみ、その両方が描かれているからこそ、聴く者は慰みを得るのかもしれない。というより、両方が描かれているのに、それを殊更に訴えるのではなくあくまで一場面、ワンシーンとして提示するだけなので、受け取り手は自由に自分の感情を喚起できるのだ。そもそも、考えてみるとこのソナタはソナタという名前だけどソナタではない。AでありノットAでもある、AかつB、みたいな。僕は戦時中の作品の中に、相反するものの混在、そしてそれが大いなる喜びで終わることを見出してああだこうだ言いたいわけではないが、この曲のフィナーレを聴いた後、少し不安感が減っているような静かなカタルシスがあるのは、気のせいでもないだろう。
最新の学術的な議論のトレンドは知らないけれど、近年、ここ十年とか数年くらいは、一般的な音楽ファンやメディアの間でも、教科書的な「印象派の祖」のようなドビュッシーの扱いに関して、それだけではなく象徴主義や前衛という観点からも論じましょうね、という流れがあるように思う。それはそれで大変良いことだけども、この最後の作品であるヴァイオリン・ソナタが、それこそ絵画の方でまさしく「印象派」と呼ばれた画家たちの作品を彷彿とさせるような音楽になったというのが、個人的にはちょっと興味深いところだ。
具体的に何かを描いているのではないかもしれないが、あたかも描写対象が存在しているかのように思わせる。その対象が持つ雰囲気のみを掬い出すように描くその描き方……それは「ドビュッシーそれすなわち印象派」という、現代の芸術界隈がやたら避けたがる評価そのもののようにすら思う。
デンマークの詩人/音楽評論家でもあるJesper Lützhofは、ドビュッシーのヴァイオリン・ソナタについて「音楽はここでは、光と影、色、瞬間のスナップ、そして漂う香りの響きである」と書いた。これ以上でも以下でもない。確かに古典や民謡からの影響だってあるだろうし、詩的なものもあるかもしれないが、全くもって表に出るものではない。光と影と色彩――それは20世紀初頭のパリの、あるいは録音であれば録音された当時の、また生演奏であれば今その瞬間の、場所、季節、時間、天気、その場その時の雰囲気を切り取ったもの。時間と空間を超えることのできる印象派絵画なのだ。
必ずしも人生最後の作品がその芸術家の総決算であるべきとは思わないが、あれほどに激しく恋に生き愛に生きたドビュッシーであれば、それこそ最後のソナタにはプルーストのヴァントゥイユのような熱い愛の歌が出来上がってもおかしくないのではないか。いやいや、そんなところ、かすりもしないのだ。プルーストが思い描いたフランス・ヴァイオリン・ソナタの愛の音楽はサン=サーンスやフォーレ、あるいはフランクであって、スワンとオデットの恋に色男ドビュッシーはお呼びでなく、むしろドビュッシーはモレルが弾く前衛のシンボルとしてお呼びがかかったのだった。今や日本では「印象派」という言葉の人気取りで売れ線なところが嫌なのか、おフランスのお上品さに憧憬の眼差しなんて暇なマダムと初心者さん御用達で手垢がついたと見なし「それそろ脱印象派で売っていこう」としたがる逆張り業界人もいるだろうが、当時は確実に、ドビュッシーは、印象派は、新しかった。革新だった。淡い光と影のスナップはきっと戦争で傷ついた人たちをも癒やしたことだろうし、今もなお、この音楽はそれが可能だと思う、このドビュッシーのヴァイオリン・ソナタという曲は。
 Author: funapee(Twitter)
Author: funapee(Twitter)都内在住のクラシック音楽ファンです。コーヒーとお酒が好きな二児の父。趣味は音源収集とコンサートに行くこと、ときどきピアノ、シンセサイザー、ドラム演奏、作曲・編曲など。詳しくは→more