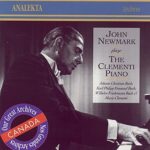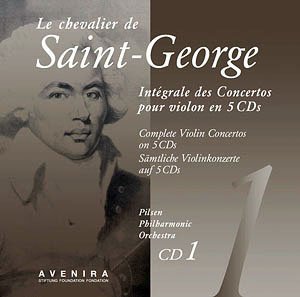カントルーブ 組曲「高地にて」
とてつもなく美しい傑作「オーヴェルニュの歌」で有名な作曲家、ジョゼフ・カントルーブ(1879-1957)の作品を取り上げよう。僕がブログで「オーヴェルニュの歌」について書いたのが2014年、もう10年も経ったのかと驚いてしまう。10年も経てばクラシック音楽界隈も様々な変化があり、昨年はイギリスの独立系レーベルHyperionがユニバーサルに買収され、大きな話題になった。Hyperionはサブスク配信されないだろうと見込んで沢山CDを買っていたので悔しい(?)気持ちだが、より多くの人が素晴らしい演奏・録音に気軽にアクセスできるようになったのは良いことだと前向きに捉え、現状Hyperionでないと聴けない曲を紹介したい。それがカントルーブの初期作品、ヴァイオリンとピアノのための組曲「高地にて」(Dans la montagne)である。
「オーヴェルニュの歌」以外のカントルーブ作品の録音は非常に珍しく、さらに室内楽作品となると一層少ない。この組曲「高地にて」は、現存する貴重なカントルーブの室内楽作品である。カントルーブが子供時代から親しんだ「山」を主題に用いた作品。カントルーブは子どもの頃、学校が休みの日には父と一緒にロット地方のバーニャック近郊にある先祖代々の家、マラレ城周辺の山岳地域をよくハイキングしたそうだ。
「カントルーブは1901年からスコラ・カントルムで学んだ」と書かれることもあるが、厳密にはスコラ・カントルムに入学したのは1907年。1901年は文通でダンディの指導を受け始めた時期だ。要は通信教育である。オーヴェルニュ地方、アルデシュ県のアノネーに生まれ、幼い頃からショパンの弟子アメリー・デゼールにピアノを学び、1896年、17歳で父親の死をきっかけにボルドーへ。銀行で働こうとするも上手くいかず帰郷、実家はオーヴェルニュの名家なので、母が亡くなる1899年まで家主としてゆっくり過ごしたそうだ。1901年に結婚、同じ時期ダンディに師事を始め、1907年にダンディの強い勧めもありスコラ・カントルムに入学、第一次大戦の開戦までパリで過ごした。
組曲「高地にて」は1904 年から1905 年にかけて作曲。楽譜をダンディに送り、アドバイスが書かれたものを返送してもらい、それを直してまた送り……と繰り返し指導を受けている。ダンディはこの曲について「私が最も興味を持ったあなたの作品であり、(その大衆的な印象とは裏腹に)最も真に独創的であると思う」と書いた。カントルーブにとって初の公式作品と言ってもいいだろう。1907年に国民音楽協会で初演された。
4曲からなる組曲で、演奏時間は30分を超える。Hyperion盤ではフィリップ・グラファンとパスカル・ドヴァイヨンの2003年録音が聴ける。グラファンのマイナーレパートリーに対する挑戦については2013年にブログに書いているのでご参照ください。
第1曲En plein vent(開けた風の中で)。なんと美しい広がりだろう。ヴァイオリンからもピアノからも、清々しい空気の振動を感じる。構成要素はいたってシンプルだが、そこに惹かれるものがある。リムスキー=コルサコフのシェエラザードのように優しく語るようなヴァイオリンを想起できるし、ピアノからはショパンのようなロマンティシズムも感じ取れる。
第2楽章Le soir(夜)、ダンディはこの楽章に非常に感銘を受け、手紙で細かく批判している。「構成は良くないが要素は全て良い」や「素晴らしい序奏、ここからどう転調して抜け出すのか」等々コメントし、最後には「もっと構成を練れば非常に良いものができる」と励ましている。ダンディが評価するのも納得の、独特の雰囲気を持った楽章だ。山の夜、夏の夜を、半音階的な色彩でもって巧みに描いている。シマノフスキやスクリャービンのような少し不思議な陰影も感じるし、フランクのソナタで親しんだような雰囲気も感じられるが、彼らともまた違う音楽。後半の妙に抒情的な運びが実に良い。
第3曲Jour de fête(祝祭の日)、ギターを模したピチカート、3拍子のリズムはスペイン風の舞曲を思わせる。民族舞曲的な楽章だ。リズムの繰り返しも変化も楽しいし、陽気さ、熱気、勢いもある。ここでもシンプルな素材を活かしており、あまりいじくり回すこともないが、それでも最後の方は絶妙なセンス。冒頭のリズムに戻って締めくくられる。
第4曲Dans le bois au printemps(春の森の中で)、輝くようなピアノに、カントルーブらしいヴァイオリンの美しいメロディが春の喜びを優しく歌っている。オーヴェルニュの歌も思い出す。この曲の冒頭部分について、ダンディは「ドビュッシー主義を信用するな、すぐに過ぎ去る」として、いわゆる印象派風に聴こえる部分を批判している。これがどの程度変わって現状なのかは不明だが、ドビュッシー風、あるいはリスト風とも取れるピアニズムは効果的に作用しているように聴こえる。あくまで現代人の僕にとっては、だけども。ダンディらしい、堂々たる再帰も登場し曲を終える。
「カントルーブはオーヴェルニュの歌だけではない、こんな名曲もある」と言いたいところだけど、若書きなのもあり、オーヴェルニュの歌ほどの圧巻の出来栄えとは言い難い。しかし、ダンディが惚れ込んだ理由は十分にわかるし(ボストンから手紙を返信したこともあったそうだ)、後の傑作の萌芽は確実に見られる。子どもの頃から親しんだ山の情景。シャトー・ド・マラレはスペインにもほど近く、そちらの舞踏音楽も聞こえていたかしら。あるいは高地の冷たく澄み切った空気は、北欧の音楽に似た空気で表されるものなのかもしれない。そこに師ダンディの学術的な薫陶も加わって……と、そんなことも思いながら、カントルーブの独創性を味うのも楽しい。
 Author: funapee(Twitter)
Author: funapee(Twitter)都内在住のクラシック音楽ファンです。コーヒーとお酒が好きな二児の父。趣味は音源収集とコンサートに行くこと、ときどきピアノ、シンセサイザー、ドラム演奏、作曲・編曲など。詳しくは→more