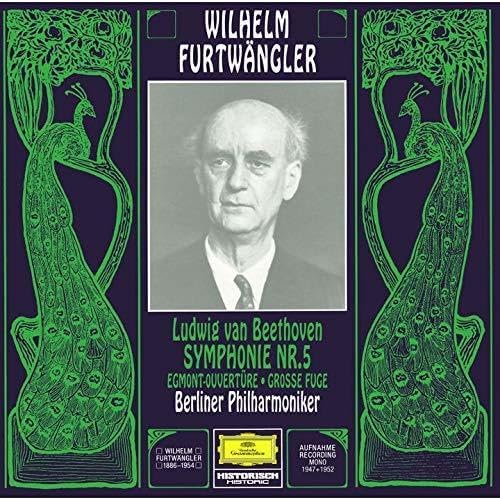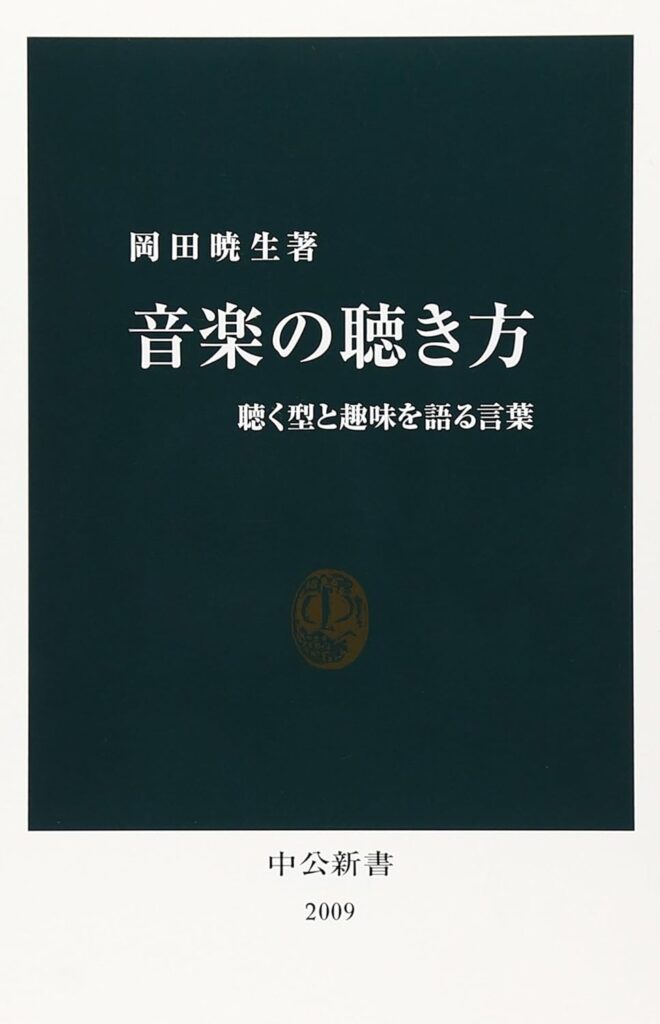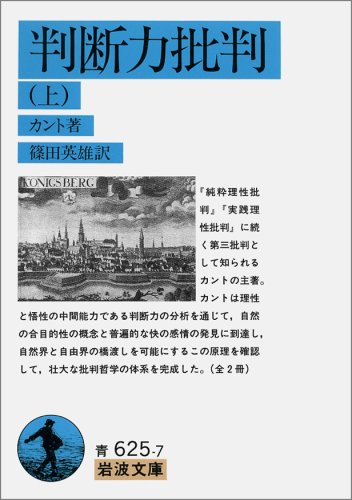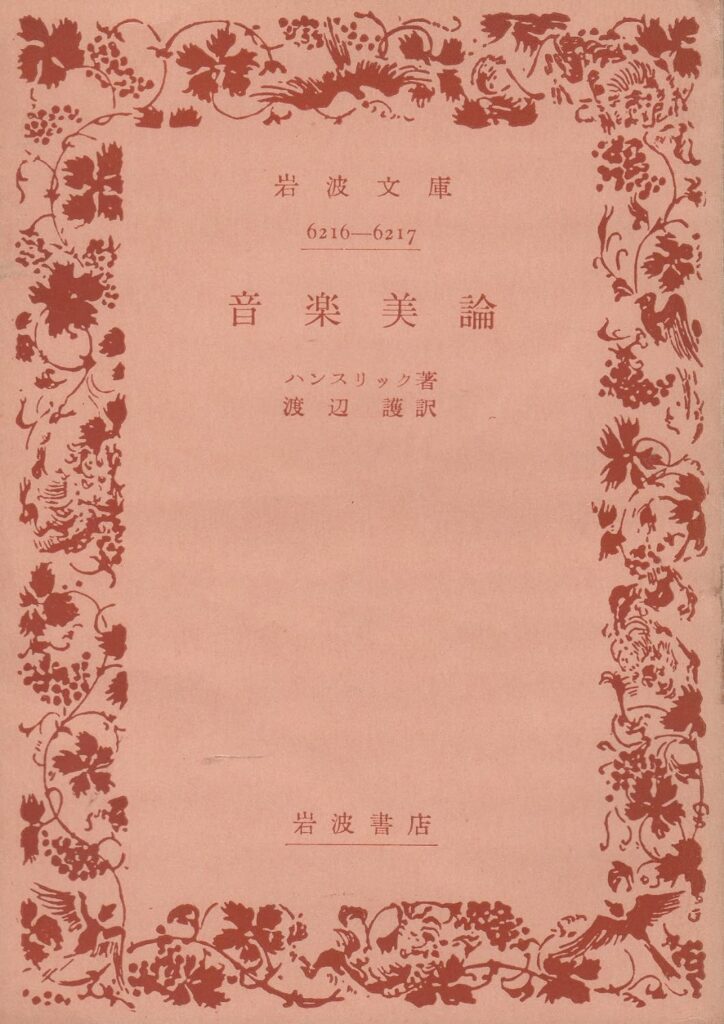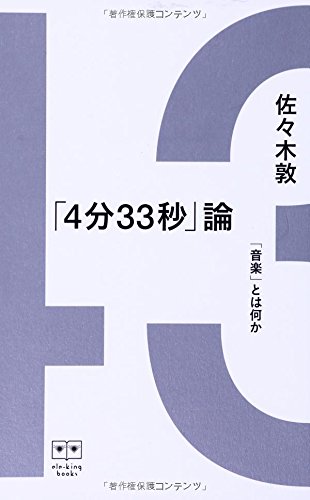カッコいいタイトルを付けてみたが、これは別にどこかのビジネス誌の有料会員記事でもないし、後日上梓するから本から抜き出してネット連載用にまとめた宣伝記事でもないし、なんならアカデミックな風を吹かしてやろうという気もさらさらない。いや、さらさらないというと嘘になるか。吉田秀和はフルトヴェングラーについて「濃厚な官能性と、高い精神性と、その両方が一つに溶け合った魅力」と書いているし、許光俊は「かつて人々が「カラヤンの音楽には精神性が欠如している」と非難したのはまことに正しかった」と書いている。この「精神性」という言葉は、使う人によって色々異なる意図が込められているだろうが、なかなか厄介な言葉だ。クラシック音楽評論で用いられる「精神性」という言葉について、もちろん僕より詳しい方は多いのは承知の上で、それでも「精神性」って何それ?とか、よくわからない!っていうクラシックのファンもいるだろうと思い、その一助となればいいなと思い書いている。
ではなぜ、今のタイミングかというと、前々からいつか書こうとは思っていたのだけど、つい先日NHKのクラシック音楽館で、エッシェンバッハ指揮N響のマーラー交響曲第2番「復活」の録画が放送され、ああ、今は「復活」か……とちょっと数年前の日々を追想してしまったからである。2011年の東日本大震災のときだった。僕は3.11の数日後、東京から金沢へ向かう夜行バスに乗っていた。友人に会うのと、チェコ・フィルの来日公演に向かうためだ。結局公演はキャンセルになってしまい、吹雪の金沢で映画館に行ったのを思い出すが、それはともかく、原発がどうなるかという混乱した社会状況の中、夜行バスでひとり聴いたコバケン指揮チェコ・フィルのマーラー「復活」は今でもよく覚えている。あるいはその翌月、仲間内で一緒に聴いたショルティ指揮シカゴ響の「復活」も。この曲のこの盤を提案したのは福島の方だった。
やはり危機的状況における音楽の意味というのは、何か特別なものがあると思う。さて、そろそろ本題に入ろう。「精神性」とは何か。僕は決して専門家ではなく、あくまで音楽ファンなので、僕の他の記事を見ていただいて「こんなやつの話は読む価値なし」と思ったら無視して欲しい。しかし、僕はこの言葉の使われ方のせいで、若いクラシック音楽ファンとご高齢のファンの間の分断を大きくしているように感じているのは事実だし、そう思っている人は僕以外にも案外多いのではないかとも思っている。
僕もどちらかと言えば若い世代(ということにしてください)なので、これは職業評論家でもブログやTwitterで持論を展開する人でもそうだけど、やたらと「精神性」を連発する物言いには首をかしげる。ただ、逆にむやみやたらに忌み嫌うのもまたどうかと思うし、音楽評論において「精神性」という言葉がどういう経緯で生まれたのかは、調べてみたり、あるいは多少知識として知っておいても良いと思うのだ。皆が皆、カントやハンスリックを読むべし、とまでは言わないけども、少なくともここに書かれる内容くらいは知っていると、他人の評を読む時に良いと思うので。それこそ精神衛生的にね。
本題:音楽史的な精神性とは
ということで、僕の見解をざっくりと。詳しいことは本読むかググってください。時代は18世紀末から19世紀、哲学者カントは『判断力批判』という著書で音楽を批判した。どういう批判かと言うと、文学や絵画などと比べ、音楽は感覚のお遊びであって、「開化」でなく「享受」に過ぎず、理性で判断すれば音楽は他の芸術よりも価値が低い、というもの。音楽関係者はショックだったでしょうね。ならば、音楽には芸術としての独自の価値は無いのか、あるとしたらどんなものなのか、音楽も他の芸術のように優れており、その存在を正当化しなければ、と当時の音楽・美学界隈は懸命に考えた。
そこで、ハンスリックなど、まあ当時の美学界隈では、音楽芸術の独自の価値は「美的体験」である、とした(ざっくり説明だからね、許してね)。それは何かというと、人間の「感性」と「精神」の統合、つまり音楽を聴いて感じた色々な「感覚的なもの」を「精神の働き」で何かしらの統一的なものとして認知することが「美」である、という価値観。どうですか、それっぽいですか? こうして音楽を正当化しようと。
当然、昔から音楽は目で見て耳で聴く感覚的なものなので(当たり前ですね)、そこに新たに「精神性」のある音楽を作ること、あるいはそういう音楽を聴くことを、より上位で価値のある行為とした。例えばハンスリックは、音楽は聴いた感覚が内容なのではなく、「音そのもの」が内容であり、その音楽の形式の中に作曲家が自らの意志を追求するのがより尊いとした。だから彼はオペラや標題音楽を否定して絶対音楽を称揚し、また民族音楽や自然の音などの美しさと交響曲やソナタ形式などの芸術的構造を持つ音楽の美しさを明確に区別したのである。あるいは聴き方についても、作曲者の込めた意志を推察して聴いて精神的な満足を得る聴き方が良いのだとした。こういう音楽の聴き方を「美的享受」として提唱したわけだ。
また19世紀は、裕福な作曲家として有名なメンデルスゾーンらをはじめとした音楽家らによって、死後忘れられていたバッハやベートーヴェンの作品を発掘・研究し、それを再演するという行為が好まれるようになる。そうしたメンデルスゾーンらの音楽家による個人的な古典研究がひとつ、また他方では、貴族が社交のために演奏会に行っていたモーツァルトの時代とは異なり、中産階級が音楽を楽しむ目的で演奏会に行くようになったことで、過去作品の再演を希望する市民の声が大きくなってきたというのがひとつ。このように、ちょうど需要と供給のマッチングが起こった結果、いわゆる「過去の巨匠」が誕生したのだ。
再演が増えればなおのこと、権威ある巨匠には単に「聴いて良い感じだな」という感覚的な満足ではなく、もっと上位の価値が求められ、例えばバッハはどんなときも神に仕えたとか、ベートーヴェンは困難に立ち向かうといった。イメージやストーリーが後付けされていく。実際のところバッハが宗教的な理由とは関係ない事情で作曲したり、あるいは宮廷の楽しみのためや舞踏をベースに作曲したことだって多かっただろうが、後付けで「バッハそれすなわち崇高な精神」と捉えられる伝説的な話が伝記に盛り込まれていくのだ。巨匠は高邁な「精神」を持ち音楽でそれを表現した人物として、精神性のある音楽として解釈するのが正しいとされるようになる。またヴィルトゥオーゾ音楽の出現に対しても、あるいは一般の娯楽音楽に対しても、それとは違う芸術音楽の価値を保証するものとして「精神性」が求められるようにもなる。初期ロマン派音楽の時代は、バッハやベートーヴェンら過去の古典派音楽や、ブラームスなどの絶対音楽を追求した音楽家に「精神性」という価値を与えた時代だったと言えるだろう。
こうしてドイツ音楽は「精神性」という武器を手に入れ、19世紀半ば以降フランスやイギリスでも、ドイツ音楽こそクラシックの本流として崇められ、コンサートのプログラムでも支配的になっていくのである。もちろんそうなっていく理由は「精神性」だけではないが、この概念の輸出について言えば、例えば日本のクラシック音楽受容についてもドイツ音楽中心主義がよく指摘され、これはお雇い外国人などの日本独自の事情こそあれ、そもそもドイツ音楽中心主義は19世紀以降の西欧全般の傾向であり、それをそのまま日本も輸入したわけであり、ドイツ音楽=精神性という図式もそのままやってきたと言える。まあまあ、異論反論はあるでしょうが、ざっくり言えばね。
日本の音楽評について
ところで、冒頭でも少し例を挙げたが、日本のクラシック音楽評で「精神性」がどのような文脈で使われてきたかは、おそらく僕よりも上の世代、ご高齢の方々は特に多くの人が知るところだと思う。しかし果たして、常に今書いてきたような歴史的・美学的文脈を踏まえて使われてきたかというと、そこのところは甚だ疑問だ。もちろん的を射た用法も多かろうが、例えばフルトヴェングラーだけでなく、クナッパーツブッシュやシューリヒトなどを褒め称え、カラヤン以降の流通盤を貶めることが目的とされるような使用になったという実情は、残念な用法と言わざるをえない。そういう用法が、「精神性」の持つ本来の意味や価値を汚してしまい、そういう評を鵜呑みにした若いファンがアバドやラトル、もっと最近ならネルソンスでも誰でもいいけど、今の演奏には「精神性」が足りないとか適当なことを言って往年の巨匠盤ばかり褒めたり、逆に若い人たちにカウンターとして「精神性」なんてものを信じる連中は耳が悪いとか言わすことになるのだ。
さらにたちが悪いのは、当時入手困難だった巨匠の音源でも、YouTubeでも配信サービスでもなんでも、すぐ手に入って聴けてしまうから、昔の評論家が自分が苦労して入手した海外流通のみの音盤を国内入手しやすい音盤よりも高評価する際に用いていた「精神性」という言葉の化けの皮が剥がれ、なんだやっぱり巨匠と言われるけど大したことないなと幻想が崩れるし、それだけならともかく、ホイホイ言われるがままに音質の悪い古い録音を聴けばすぐに「精神性」と言い出す若者さえ生み出す可能性もある。クナでもシューリヒトでも、即時無料で聴ける時代なのだから。
元々「精神性」は、二元論的に「感覚」に対して持ち上げられたので、実際カラヤンの徹底した音響へのアプローチが極めて感覚的であることや、録音技術の向上で感覚的な享受が増幅されたことなどを踏まえると、例えばステレオ録音に慣れた人がフルトヴェングラーのモノラル録音に対して「感覚」ではなく「精神」で対峙せざるをえないというのは、聴く側の姿勢としてはあり得る。だって感覚的にはどうしたって普通のステレオ音源に比べて音質も悪いし、あるいは「天才的素人」と言われたフルトヴェングラーのオーケストラの響きへのアプローチが、カラヤンのものと全く異なるのは事実だし。
ちょっと話が逸れるが、日本の音楽評でも度々登場する「悪魔的」(デモーニッシュ)とい表現、これも「精神性」と並んでよく用いられるが、まあキリスト教としては「悪魔」という訳になるんだろうけど、デモーニッシュってそもそも古代ギリシア以降のダイモン、鬼神、いわば超自然的みたいな意味なので、どちらかというと理性的で合理的であるべき「精神性」とは逆の意味である。なので18世紀には近代芸術の価値観としては見下される方の言葉だ。だからフルトヴェングラーは演奏によって、ないしは評者によって唐突に「悪魔的」だったり「高い精神性」を持っていたりするわけだが、全くあっち行ったりこっち行ったり忙しい指揮者である。別にどちらかを否定しているわけではない。そういう演奏だってあろうが、正直あまりわからずに使っているのではないかと思うこともあるので、一応書いておいた。
「フルトヴェングラーのベートーヴェンには精神性がある」という文言は、言葉本来の意味で言えば、精神性とは音楽を聴いて感じた色々な「感覚的なもの」を「精神の働き」で何かしらの統一的なものとして認知することであるから、要は聴いた感覚で「あー良かった」ではなく、「フルトヴェングラーのベートーヴェンは聴くことで奏者や聴衆の精神活動を促す音楽である」という意味になる。ではそれは本当のところどうなのか。フルトヴェングラーが活動した当時の社会背景や彼の立場などを鑑みても、まあ100%の間違いだとは言えないのではないでしょうか。バイロイトの第九は、第二次世界大戦で6年間休止していたバイロイト音楽祭が1951年に再開した年のプログラム、このタイミングで第九を演奏されて、感覚的、音そのものの響きだけで済む人は少ないだろうね。あるいは1947年の、戦後初復帰となるフルトヴェングラー指揮ベルリン・フィルのベートーヴェン「運命」はどうでしょう。この演奏に、ああやっと共に音楽できるという指揮者やオーケストラ団員の喜びを見出すのはただの空想に過ぎないだろうが、それは聴いた音という感覚的なものを精神の働きで何かしら統一的なものとして認知する聴き方をしていると言っても間違いではない。どうでしょう、こじつけかな?笑 冗談めいて書いたが、精神性があると評される音楽や演奏については、簡単に否定するのは難しいようにも思う。では、精神性がないと評されるものはどうだろうか。
サウンド重視は精神性の欠如なのか
もう少し違う見方で言うと、感覚と精神という二分法を、「言語的」と「音響的」という分け方と一緒くたにしているせいで、非常にサウンドにこだわった演奏を、非言語的ではなく「精神性の欠如」と言ってのける技が生まれてしまったのかもしれない。この言語的というのはもちろん、アーノンクールが指摘した19世紀以前の音楽は「話し」それ以降の音楽は「描く」という視点を踏まえて今僕が言ってみただけなのだが、要は完全に言語と結びつき文節に別れ抑揚を付けて語るような演奏と、流れるようなソステヌート/レガートで作られた理解すべきではなく感じるべき演奏、という二分法のことだ。こうした演奏伝統の変化は、岡田暁生先生が著書で上げられている通り、シュナーベルの弾くシューベルトのソナタ第20番4楽章と、ポリーニやブレンデルの弾く同曲を比べるとわかるのだが、そうした明らかに「語っている」演奏ではなく、サウンドに重点を置いた(奏者本人がどう思っているかはともかく)演奏に対して、感覚的だから精神的でないという評価を下してしまっているものもあるのではないだろうか。
旧来の語る演奏の伝統が失われ、新しい感性に訴える奏法がメジャーになり、アーノンクールの言うところの「話す」演奏は古楽以外で失われつつあるのはその通りかもしれないが、現代の演奏に「精神性」が欠如しているかというと、それは何とも言えないところだ。繰り返すが、本来「精神性」とは音楽を聴いて感じた色々な「感覚的なもの」を「精神の働き」で何かしらの統一的なものとして認知することであり、よく考えれば「美的享受」するかどうかの聴き手次第なわけで、自分の今まで聴いてきた精神性ある音楽と違うからと言って即「この演奏は精神性がないからダメ」と切り捨てるのは、聴き手の怠慢なのではないか。何もカラヤンを精神性の欠如と言い切った宇野功芳ひとりを攻め立てているのではない。彼には彼の決して譲れない美学があったのだろう。問題は宇野の精神性論を鵜呑みにすることだ。フルヴェンでもクナでも、もう何十年も前の時代である。よくよく現代という時代の持つ時代精神を理解し、あるいはその音楽の持つ本質的な構造やスコアなどを理解し、その上で演奏を聴いて「精神性がない」と言っているのであれば結構なことだ。だが結局はフルトヴェングラーと同じ「精神の活動」を期待している人には、昨今の演奏からはきれいなサウンド以外に何も見いだせないのだろう。そういう人は多いのではないか。カラヤンでも、ヤンソンスでも、なんならキリル・ペトレンコでもいいが、磨き上げたサウンド以外には何も見いだせないという人が。僕は初期ロマン派に生きる評論家ではないので、聴いた感覚を楽しむ聴き方だって大いに素晴らしいと思っている。何しろ時代が違うからね。聴いたときの感覚を、あれこれ考えて、ああ、この音楽は、こういうことだったのか!と判断したとしたら、それは精神性の高い演奏がそうさせたのだし、精神性を意識した聴き方なのだろう。
これはある意味、戦時中という特殊な状況があれば簡単だったのかもしれない。誰もが音楽に何かしらの意味を見出し、求めていた時代。戦後にしろ、20世紀後半はオーケストラが持つ意味、クラシック音楽が持つ意味が、今とは全く違っていたから言えたのかもしれない。教養としてのクラシックの時代から音楽の趣味の多様化、様々な変化があって当然だ。しかし、どんな変化があろうが、どの時代にも人は生き、そこで音楽を奏でるのであって、誰にとっても見つけやすそうな、わかりやすく語れる「精神性」だけを拾い食いして後は見ないふりという態度は、それこそ誠実さが足りない、精神なんて単語を使うに値しない不遜な態度に思われる。もしかすると、逆に圧倒的なソノリティを作り出す音楽こそ、現代における真の精神性ある音楽なのかもしれないしね。
精神性の時代に向けて
今、世界的に流行っているこの新しい疫病のせいで、第二次世界大戦以降の最大の危機、なんて言われる状況がやってきてしまった。街からは音楽が消えつつあり、それでもいつか、この危機を乗り越えたら、再び音楽を、と切望しているのは皆同じだろう。乗り越えられなかったらどうしようもないが、これを乗り越えたとき、まさにそのとき、再び「精神性」が活躍する時代が来るのではないか。久しぶりに集まったメンバー、久しぶりに聴く聴衆、奏でられるのは「運命」か、「第九」か、あるいは「復活」か……それに対して、日頃「精神性」を信奉する/忌避する人たちは、音楽家は、評論家は、愛好家は、どう「感じ」、どう「考える」のだろうか。「考えるな、感じろ」のように、ただただ音を浴びて歓喜する者もいるだろう。しかし聴いた感覚から、普段には考えられないような勢いで平和、健康、感謝、絆、愛、友情などを見出す者もいるだろう。だとしたら美的享受を訴えていた18世紀の音楽評論家も泣いて喜ぶのではないだろうか。きっと「精神性」という言葉が、ある種の音楽を崇め奉る目的や、非難する目的の言葉としてではなく、まさしく時代精神を反映し、音楽という感覚の芸術が現代を生きる者の精神に何を与えどう動かすのかを記録するために用いられる、そんな時代が来るだろう。僕はそう望んでいる。
危機的状況がないと精神性ある演奏が生まれないのだろうか。もっとも、音楽の危機を救うために生まれた概念なのでそれでも良いのかもしれない。どんな演奏をしても、どんな聴き方をしても、自由だし正解はない。ただ間違いはある。「精神性」という言葉は、そういう意味では多くの場面で間違った使い方をされてきた言葉だと思う。またそのせいで、ファンの世代間闘争のような、しょうもない争いを生んでしまった原因でもあると思う。もちろん正しい使われ方をしてきたときもあると思う。僕は感覚的に聴くのも好きだし、(足りない頭で)あれこれ考えて何かしらの精神活動をしていると思うような聴き方をするのも、もちろん好きだ。だから安易な使い方をして、大して意味もわかってないくせにシューリヒトのブルックナーにはドイツ音楽の精神性が云々などと語りその言葉の本来の価値を貶めて欲しくないし、逆に安易に否定して、音楽が精神に働きかけて愛や絆などの言葉を実感させたり、ストーリーを描く行為を鼻で笑うようなことはして欲しくない。いかにせよ尊い、本当に尊いのだ、音楽は。音楽を愛する人は、今なら誰もがそう思ってくれるのではないか。
 Author: funapee(Twitter)
Author: funapee(Twitter)都内在住のクラシック音楽ファンです。コーヒーとお酒が好きな二児の父。趣味は音源収集とコンサートに行くこと、ときどきピアノ、シンセサイザー、ドラム演奏、作曲・編曲など。詳しくは→more