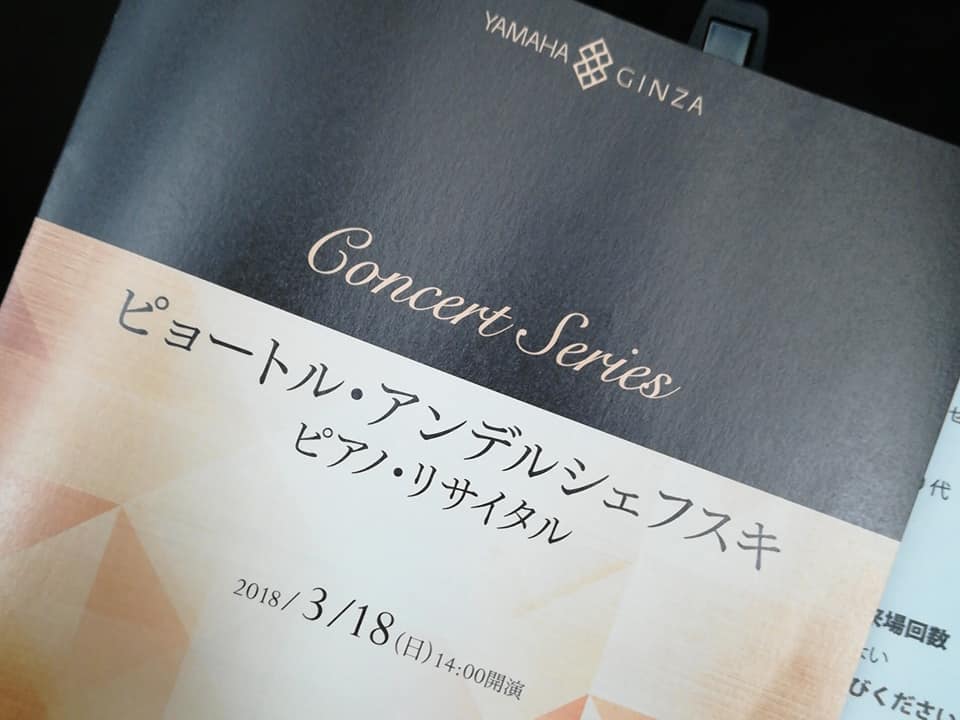ヤナーチェク カンタータ「アマールス」
この曲を聴いて感動しないことなど決してありえないだろう。チェコの作曲家ヤナーチェクの残したこの5楽章のカンタータは、曲といい歌詞といい、本当に聴くものに感動を煽る音楽だ。
1897年に作られたこの作品は、ヤナーチェク自身の苦しかった少年時代の記憶が投影されている音楽だと言われている。ヤナーチェクは田舎の貧乏で子沢山な家庭に生まれ、口減らしの意図もあって、11歳のときにブルノの修道院学校に送られた経験がある。
この苦い少年時代が、チェコの詩人ヤロスラフ・ヴルフリツキーの書いた詩とリンクする。恵まれない少年アマールスが主人公のこの詩は、ヤナーチェクの心に深く響いたに違いない。
「アマールス」は、ラテン語で「辛い」や「苦い」という意味の言葉である。不義の子のためその名で呼ばれる少年は、修道院で日課をこなす日々を過ごすある日、若い恋人たちが祈りに来るのを目撃する。その様子を見ていたアマールスは、今まで触れたことのない「愛」というものに触れ、得も言われぬ感情が湧き上がり、祈りを終えた恋人たちの後を付ける。するとそこは墓地で、美しい自然と愛に満ちた恋人たちの様子に、アマールスの愛の感情がついに爆発する。そしてそこでアマールスは息を引き取る、という筋書きである。
ストーリーだけでも感涙必至だが、それにヤナーチェクの、また特に気持ちが込められているであろう音楽となれば、名曲にならないわけがない。
オーケストラと、混声合唱、ソプラノ、テノール、バリトンという構成。歌詞はもちろんチェコ語である。バリトンがナレーター、ソプラノは天使の声、テノールがアマールスを演じる。初演は1900年だったが、演奏がまずかったため不評でその後15年も再演されなかった。今も録音も多くはない。見落とされがちな作品だが、こうして少しでも多くの人に知ってもらえたら幸いである。歌詞はこちら。
1楽章、モデラートの序奏は短調で始まる。バリトン独唱で舞台設定が歌われると、悲しげに合唱が応える。
2楽章ではまず合唱がアマールスの佇まいについて、静かだが力強く、切実さをもって表現する。彼は「何か未知なるもの」(neznámého)を求めるように思い沈んでいるのだ。そしていよいよテノール独唱でアマールスが歌う。高音から始まり高音に終わるこの歌唱を聴けば、その暗い運命を痛ましく思うに違いない。オーボエのソロと木管楽器がまたアマールスの人物を描くのを助けている。
3楽章はテノールが、つまりアマールス自身が語りストーリーを進める。祭壇の前の灯明に油を注ぐことが日課だった彼が、「私の魂の火を点しているのだ」(Rozsvěcuji svoji duši)と繰り返し歌う部分は印象的だ。
恋人たちが祈りを捧げるシーンでは音楽は幸福に満ち、後を追う部分では音楽は徐々に徐々に勢いを増す。平明な描写で、聴く者はすぐに場面を思い浮かべることができる。
花が香り鳥が歌う、美しい墓地に着き、アマールスは感情がはちきれそうなる。この部分の音楽を聴くと僕も胸がいっぱいになる。ふと落ち着き、アマールスは、見たことも会ったこともない、母親のことを思い出すのだ。自分をこんな運命に産み落とした母親のことを。ハープが静かに楽章を結ぶ。
4楽章はナレーターのバリトンが悲劇の始まりを告げる。アマールスは油を注がなかった。ヴァイオリンのソロはアマールスの魂だろうか。鳴き続ける鳥の声はフルート。ファゴットに導かれた合唱が、生みの親の墓の上に横たわるアマールスを歌う。合唱の裏のヴァイオリン・ソロは、死して幸福に満たされたアマールスの魂ではないだろうか。
最後の5楽章のエピローグでは、ティンパニ、弦、金管とチャイムが鳴り響き、生前の不幸と打って変わって、明るい春の自然にアマールスを迎え入れる神の温かな計らいが見られる。この救済があるからこそ、僕はこの曲が大好きだし、また名曲たる所以だと思うのだ。
1楽章で辛く厳しく歌われた「その名はアマールス」(tož Amarus jej zvali)が、エピローグで静かに静かに「その名はアマールス」(Amarus jej zvali)と歌われるのには、覚えず鳥肌が立つ。
 |
マルチヌー:戦場ミサ、ヤナーチェク:アマールス マッケラス,サー・チャールズ・マッケラス,チェコ・フィルハーモニー管弦楽団,プラハ・フィルハーモニー合唱団,クヴェストラヴァ・ニェメチュコヴァー,レオ・マリアン・ヴォディチュカ,ヴァーツラフ・ジーデク 日本コロムビア |
 Author: funapee(Twitter)
Author: funapee(Twitter)都内在住のクラシック音楽ファンです。コーヒーとお酒が好きな二児の父。趣味は音源収集とコンサートに行くこと、ときどきピアノ、シンセサイザー、ドラム演奏、作曲・編曲など。詳しくは→more