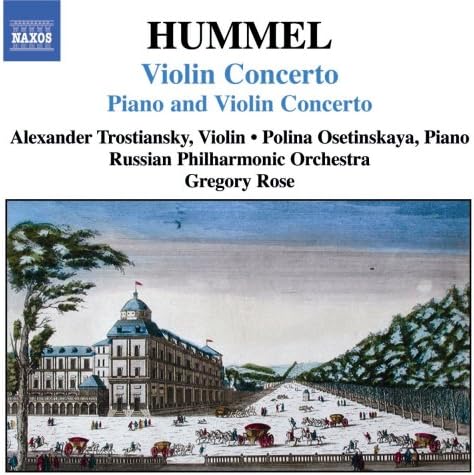フンメル ピアノとヴァイオリンのための協奏曲 ト長調 作品17
モーツァルトの弟子でベートーヴェンのライバル……なんてカッコいいポジションにいる作曲家なんだ、フンメルは。作曲家であり当代随一のピアニストでもあったヨハン・ネポムク・フンメル(1778-1837)。8歳でモーツァルトの弟子となり住み込みでピアノを師事、その後も長く友情を育んだそうだ。サリエリやハイドンにんも学び、ハイドンの後継としてエステルハージ家の宮廷楽長に就任。ベートーヴェンと並ぶ有名人となり、ベートーヴェンの葬儀では喪主を務めている。
フンメルの代表作でもあるピアノ協奏曲は作品番号のあるものだけでも5曲あるが、モーツァルト風の初期作品から徐々にロマン派の原型とも言える様式に変化し、メンデルスゾーンやショパンを予感すると評されている。今回取り上げるのはそのピアノ協奏曲ではなく、ピアノとヴァイオリンのための協奏曲。1804-1805年の作品で、ちょうどフンメルがエステルハージ家で働き始めた頃の作品。まだ明らかにモーツァルトの影響が見て取れるし、おそらくモーツァルトの協奏交響曲に触発されたのではないかと言われている。
ピアノ協奏曲もヴァイオリン協奏曲も、協奏曲の分野では二大人気の協奏曲だけど、「ピアノとヴァイオリンのための協奏曲」というスタイルの曲は、クラシック音楽の長い歴史の中でも極僅かしか存在しない。ハイドンが1766年頃に作っているし、1778年頃にモーツァルトも手掛けているが未完に終わっている。現代で最も演奏・録音が多いのはメンデルスゾーンの協奏曲で、この協奏曲もメンデルスゾーンがフンメルから学んだ際に影響を受けたものだと指摘されている。
伝統的な3楽章構成で30分ほど。1楽章Allegro con brio、まるでモーツァルトを思わせる序奏。ピアノが主題を奏で、続けて主題はヴァイオリンに移りピアノは伴奏に。ピアノとヴァイオリンの共演に、弦楽や木管が華を添える。ソリストたちはよく互いを引き立て、ときに競争する。そうしたソロ楽器を追うのも楽しいが、全体の雰囲気も上品で素敵だ。
2楽章Theme and Variations、この楽章は白眉、フンメルの得意とする変奏曲。この変奏曲という形式は、2つの個性的な楽器をオーケストラの中で活躍させるのにぴったりだろう。オーケストラの他の楽器も含め、大小様々な組み合わせで目眩く変奏曲が展開される。これが美しいのだ。まったく転調がないのも、フンメル自身も楽器の音色だけで十分彩り豊かだと考えたからなのではないか。
3楽章Rondo、この楽章も楽しい。フンメルの自在なアイディアに驚かされる。ピアノとヴァイオリンも速いテンポで巧みに絡み合い、とても美しい。ここまでずっと長調だったところで、最後の楽章の中間部になってロマンティックな短調のメロディを挟むのもまた良い。
それにしても、「一つの楽器が主役」というのは、いかにわかりやすく物事を語るか、これがよくわかる。言い換えれば、この曲の主人公が誰なのかは、やはり若干ぼやける。多くの作曲家たちがノータッチだったジャンルというのも頷ける。この曲でも、ソロ楽器として捉えるべき音が「ピアノ」「ヴァイオリン」「ピアノとヴァイオリン」という3パターンあり、しかも「ピアノとヴァイオリン」というデュオ形式は、例えば「フルートとオーボエ」とか「ヴァイオリンとチェロ」とかと違い、圧倒的にもう必要十分というか、これだけで完結しているという雰囲気がある。逆にもう1つ加わって三重協奏曲とか、それ以上になればもはやコンチェルト・グロッソ的にも扱えるだろうが、この二者だけという構図は、どうにも特別な扱い難さがあるだろう。
ピアノもヴァイオリンも、それぞれ単独での完全性が強い楽器で、私こそパーフェクト、私が主役、という我の強さみたいなのが魅力でもある。それを活かすのが協奏曲の醍醐味でもあるわけで、打ち消し合ってしまっては元も子もない。それでも、フンメルは上手く扱っていると思う。特に変奏曲楽章では様々な輝きが見られるという魅力がある。これは独自性が高いし、外側楽章もまた生き生きした主題そのものの美しさのおかげもあって、聴いていて楽しいのは間違いない。「私達こそがパーフェクト!」という楽しさと「ここにいる皆が主人公」的な楽しさと、その絶妙なバランスが取れている稀有な作品だ。
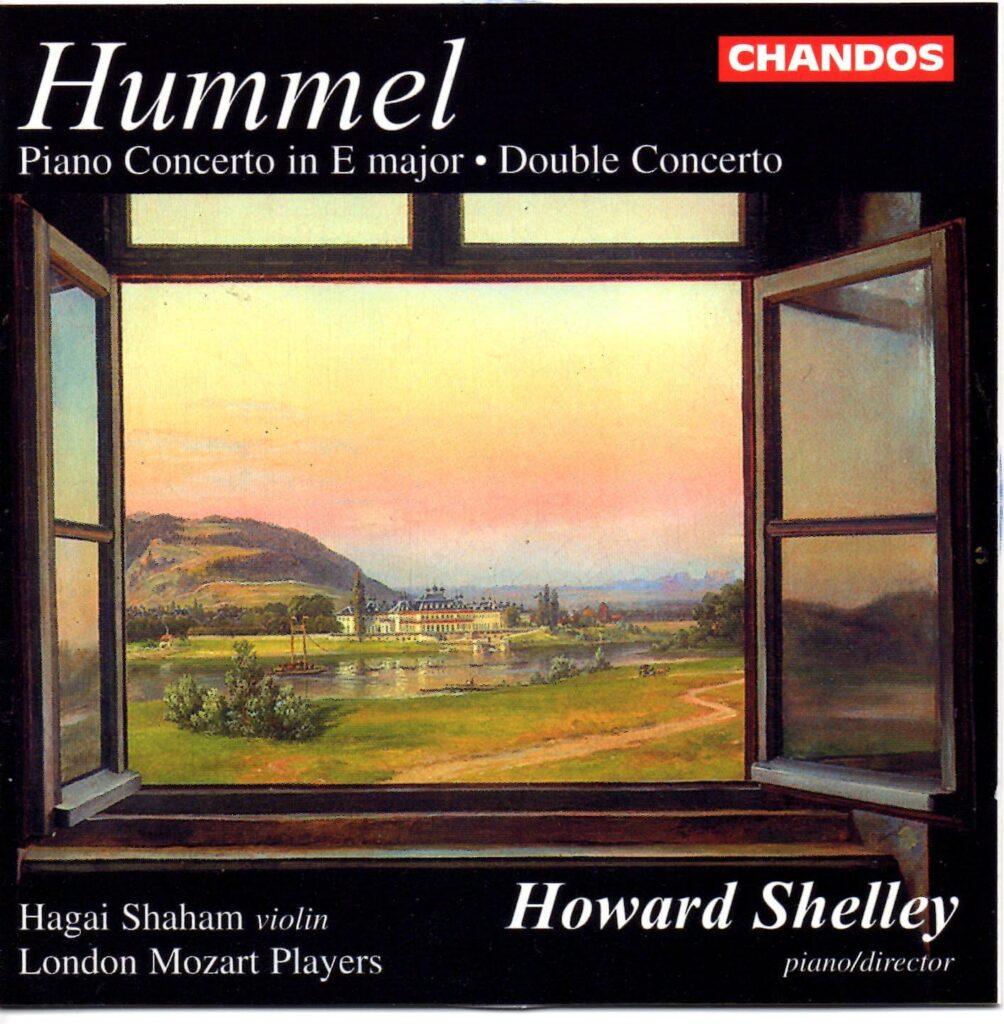
Hummel: Piano Concerto in E major
 Author: funapee(Twitter)
Author: funapee(Twitter)都内在住のクラシック音楽ファンです。コーヒーとお酒が好きな二児の父。趣味は音源収集とコンサートに行くこと、ときどきピアノ、シンセサイザー、ドラム演奏、作曲・編曲など。詳しくは→more