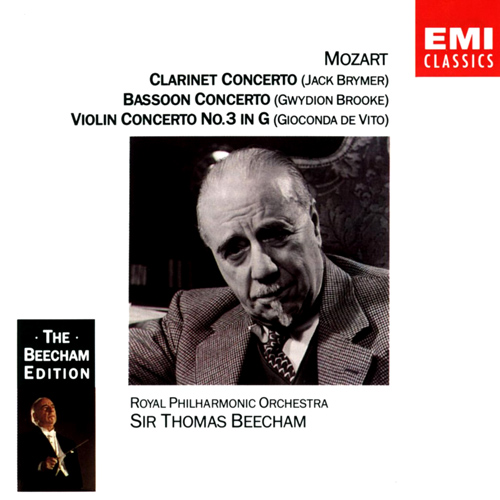モーツァルト ファゴット協奏曲 変ロ長調 K.191
2022年からは年に一回ずつのペースでモーツァルトの曲についてブログを書いている。2022年はディヴェルティメントK.254、2023年はピアノ協奏曲第20番K.466、2024年は交響曲第36番「リンツ」K.425。別に年に一回じゃなくても、二度三度書いたって良いのだけど……今年は何にしようかなと思い、よし、ファゴット協奏曲にしとうと決めた途端、指揮者クリストフ・フォン・ドホナーニの訃報が入ってきた。素晴らしい録音を多く残してくれた名指揮者で、残念至極である。
ドホナーニはモーツァルトの名演も多い。特にファゴット協奏曲については、ドホナーニ指揮クリーヴランド管(独奏デイヴィッド・マクギル)の1993年録音が、個人的には数ある同曲の演奏の中でも5本、いや3本の指に入ると言っても過言ではないくらい、好きな演奏なのだ。この曲の佳演に多い室内オケとは違い、大きなオーケストラを完璧に導くドホナーニの手腕、オケとソリスト(同オケの首席ファゴット奏者である)の間のやり取りも互いを引き立て共に高め合うような素晴らしさで、常にバランスも良く美しく響く、本当に最高の演奏の一つだと思う。ということで、偉大な指揮者の追悼として冒頭にその録音を貼ることにした。ドホナーニ、どうぞ安らかに。
モーツァルトの曲は、割と今までも色んな編成・ジャンルの曲を取り上げてきたつもりだが、管楽器の協奏曲はまだ一つも取り上げていなかった。やっぱりモーツァルト好き兼管楽器好き(2021年にはグラン・パルティータでブログ更新している)としては、管楽器の協奏曲に触れずして一生を終えるわけにはいかないので、そろそろ書いてみないといけないかなと思ったのだ。
ではモーツァルトの管楽器協奏曲の中で最初に挙げるべきは何か。どれも傑作だが、このブログならファゴット協奏曲でしょう。多分、一番陽が当たらない曲だと思うので。それでもモーツァルトという巨大ブランドだし、陽は当たりまくっているけれども、その中で敢えて言うなら、という意味でね。解説はWikipediaを、と思い見てみたがあまり熱量がなさそうなため、マリモのページを見てもらうのが良いかもしれない(リンクはこちら)。K.191がモーツァルトの唯一現存するファゴット協奏曲であり、1774年に作曲された。モーツァルト18歳の作で、フルート、オーボエ、クラリネット、またホルンの各協奏曲よりも早い。
モーツァルトより少し前の時代、つまりグルックらの時代のファゴットはどのような扱いだったのか。オーケストラの中で低音を補強する役割だったファゴットが、グルックらの時代になるとヴァイオリンやヴィオラといった高音を支え、その倍音を増やす役割を担うようになる。またファゴットだけのオブリガートなども使われるようになる。独特な仄暗い音色を表現の幅として活用し出すようになるのだ。ハイドンは交響曲でその地固めを行い、交響曲はファゴット2本、という慣習もできてきた。交響曲はもちろん、ハイドンはオラトリオ「天地創造」でもコントラファゴットと共に重要な役を担わせている。
そしてハイドンに負けず劣らず、モーツァルトはオーケストラの彩りを豊かにする手段としてファゴットを重用した。最も有名なモーツァルトのファゴットはなんだろう、協奏曲を除けば、フィガロの結婚序曲の冒頭かなあ。弦楽器に加わるファゴットの音色、これがあるとないとでは大違いだ。なんなら弦楽器が場面全体を表すとしたらファゴットがフィガロという人物だと言ってもいい。言い過ぎか? こうしたヴァイオリンのオクターブ下、あるいは2オクターブ3オクターブ下をユニゾンするファゴットを「ウィーンのユニゾン」と呼ぶこともあるらしい。確かにウィーン古典派らしい響きだと思う。
クラリネット奏者でモーツァルト研究者でもあったMartha Kingdon Ward(1938-2021)は、モーツァルトによるファゴットと他楽器の組み合わせについて次のように指摘した。いわく、クラリネットと合わせると温もりが出て安定感があり、フルートと合わせるといっそう落ち着きのない空虚感が出るが、これらの組み合わせが平和的になることは滅多になく、「ヴィオラとファゴット」という稀有な組み合わせにおいてこそモーツァルトのファゴットは異様なほどに暗い音色を呈し、他の管楽器とは全く異なる説得力、威厳ある空気を醸し出すのだ、と。色んな音色の重なりがあるが、確かにファゴットはヴィオラと合わさると絶妙な雰囲気を生むのは間違いない。
モーツァルトのファゴット協奏曲は自筆譜が失われており、詳しくわかっていない点も多い。ウィーンのアマチュア奏者のために書かれたとも、宮廷の楽団が演奏するために書かれたとも言われる。カデンツァも不明だ。奏者は皆、自作か過去の有名奏者のものを用いる。録音で聴く際も、結構な割合で作者不明のカデンツァを吹いていることが多い印象である。作者不明というか、用いているカデンツァの詳細を載せてくれないことが多いというか。たまにえらく長いカデンツァもあって面白い。
全体は20分弱のコンパクトな協奏曲。1楽章Allegroでは序奏に続いてソロが登場。跳躍あり、トリルあり、速いフレーズもあり、登場の瞬間から魅了してくれる。先程のWardの言葉ではないが、跳躍もあまりポンポンやられると普通ならどこか滑稽というか、コミカルでユニークな雰囲気が先行するものだが、ここではその跳躍があるおかげで威厳が出るように感じる。堂々たる登場だ。こういう風にできるのはモーツァルトの天才的なところだ。様々な学者らが古くから指摘するように、この曲はファゴットでなければ魅力が十分に伝わらない、チェロなどの編曲では上手くいかないという作りになっているのも、この曲の価値を非常に高めている。僕は特にトリルの多用でそれを感じる。本当に愛おしいトリルたちである。
2楽章Andante ma adagio、美しくないわけがない、モーツァルトの緩徐楽章。哀愁とその美に満ちている。楽譜の出版はモーツァルトが晩年になってからだが、売れ行きは好調だったそうだ。それも納得できる。ちょっと違うかもしれないけど、おそらくジョン・コルトレーンの“Ballade”を初めて聴いた60年代の人たちの感動というのは、18世紀にモーツァルトのファゴット協奏曲の2楽章を聴いた人たちの感動と近いのではないかと勝手に想像している。人の声に近い管楽器と言われるサクソフォン、それが登場する以前はファゴットがそのポジションだっただろう。今も音色が変わることはないし、サクソフォンよりも、同じく人の声に近いと言われる弦楽器よりも、ファゴットに似てると思うような声質の人に出会うこともある。僕自身、サックスと弦楽器とファゴットだったら、多分、自分の声はファゴット系だと思う。音域もあるけどね。
3楽章はRondo: Tempo di menuetto、優雅な舞曲による終楽章。トゥッティとソロが交互に現れ、さながらヴィヴァルディのリトルネッロ形式の協奏曲。ヴィヴァルディも多くのファゴット協奏曲を書いたし、それをモーツァルトが知らなかったはずはない。関係はどうあれ、この楽章の音楽も高貴な空気が充満している。華やかな宮廷の舞踏会、そこで最も気高く輝き踊る、一人の麗しい貴族……などと妄想する。王だろうか。それも悪くない。しかしファゴットという楽器からは王のイメージはさほど感じ得ない。もし甲高い声の管楽器ならそれはうら若き娘にもよく似合うだろうが、それよりも低い声のファゴットはどうか。威厳はあっても決して冷たくなく、人の声のようなどこか親しみやすい雰囲気もある。こうなるとつい、男装の麗人を想像するなあ。いけないだろうか。マリー・アントワネットの時代だし、いいかしら。音楽は自由に楽しむべし。
先のWardの言葉を借りるなら、「普遍的な人間性を持つファゴットは、私たちが言葉で表現するしかないあらゆる感情を、最も純粋な音で表現することができる」のだそうだ。これはさすがに、ファゴットに恋い焦がれて盲目になった人の言葉のようにも聞こえるけれど、そういう趣きもあるのは認めざるをえない。だってどうしても、不思議と人の声に近い音なんだもの。
ハインリヒ・クリストフ・コッホの『音楽事典』(1802)ではファゴットは「愛の楽器」と書かれている。またソースは謎だがよく言われるのは、ベートーヴェンがファゴットの音色を「天からの声」と表現したという逸話だ。愛の楽器、天からの声。それが「人の声」に近いというのも、なんとも含蓄ありげである。
機知に富み、華やかで技巧的なモーツァルトのファゴット協奏曲。楽器の可能性を十二分に引き出す名曲であると共に、人智を超えた天の音楽であり、また人の心に最も近づける音楽でもあると思う。本当に素晴らしい音楽である、それは何よりも、愛ゆえに。
 Author: funapee(Twitter)
Author: funapee(Twitter)都内在住のクラシック音楽ファンです。コーヒーとお酒が好きな二児の父。趣味は音源収集とコンサートに行くこと、ときどきピアノ、シンセサイザー、ドラム演奏、作曲・編曲など。詳しくは→more